>>> 介護営業のありかた (前) ~百害あって一利なし~ から続く
なぜ、大企業から零細企業まで、このような盲目的で意味のない介護営業が漫然と行われているのか。それは、事業者が介護経営や介護現場というものを、知らないし、また理解しようともしないからだ。
もう少し、突っ込んでいえば、「介護なんてどこでやっても同じ」「どんな高齢者住宅でも同じ」で、「安心・快適」と入居者、利用者をかき集めてくることが介護経営のポイントだと考えているからだ。
こんな劣悪な経営理念は、ブラック企業の最たるものだ。
営業活動というのは、顧客にとって有為、有益な商品やサービスを売ることだ。商品力・サービス向上や労働環境改善によって、優秀な人材を育成し、顧客や地域からの評判を上げることではなく、「紹介業者に払う紹介料がもったいないから、管理者に営業させよう」という発想そのものが、あまりに貧相で、あさましい。
残念ながら、これは社会福祉法人も変わらない。
最近は、ユニット型特養ホームも入所者が集まらなくなり、紹介業者を使ったり、介護営業を行うと頃も増えているという。その理事長、施設長と話をしても、「2040年に、この業界がどうなっているのか…」「社会福祉法人はどう変わるのか…」という長期的な視点もない。「これからの社会福祉法人の嵐の時代に今やるべきことは何か」「サービス向上や待遇改善に何を行っているのか」と聞いても、「大変だ、大変だ」「福祉を守れ」というばかりで、何一つ答えは返ってこない。「介護報酬が低いのだ問題だ~」と愚痴をいうだけの経営者のもとに、優秀な人材が集まるはずがない。
「こんな人員配置で、まともな医療対応とか認知症対応とかできると思ってるのかな」
「正直、こんなところで働かされてるスタッフも管理者も哀れだよねぇ」
現在の介護営業は、その営業先の病院や施設で嘲笑の対象となるか、もしくは面倒な高齢者・家族を押し付けられて、介護現場が疲弊し、管理者への不信を招くという二つの選択肢しかない。
こんな高齢者住宅、介護サービス事業者が増えても、入居者も家族も、介護スタッフも管理者も誰も幸せにならない。サービスの低下、優秀な介護人材の離反、離職を招いて、経営にとっても、地域社会にとってもマイナスにしか残らない。
介護営業は、他の事業所との競争に打ち勝つ唯一の方法
社会福祉法人を含め、「介護サービスに営業活動など不要だ」と言っているわけではない。
他のコラムでも繰り返し述べているように、これから後後期高齢社会が進むにつれて、介護サービス事業、特に社会福祉法人の経営環境は、制度変更リスク、入居者・スタッフの確保を含め一層厳しくなることは避けられない。その中で、「営業活動の強化」は、他の法人、事業者との競争に打ち勝つ、唯一の方法だと言ってよい。
ここでは、簡単に三つのポイントとその方向性について述べておく。
営業活動の第一の目的は、「信頼を得ること」だ。
営業の基本は、そのターゲットの抱える課題やニーズを理解し、自社の知識・ノウハウ・サービスを通じてその解決策を提供し、信頼を築くことだといわれている。特に、介護は、その地域に根付いて行うサービスであり、かつコンピューターや自動車などの製品・性能を売っているわけではないため、信頼してもらうということが、その活動において最も重要になる。
そのためには、「相手は何を困っているのか」「どんなことを欲しているのか」を理解し、介護のプロとしての有用なサービスや情報を与えなければならない。「この人は介護の問題に詳しいな」「この事業所は五年、十年先のことまで考えているんだな」「これからも仲良くしたい、いざというときに相談しよう」と信頼してもらえることが最大の目的だ。
相手に与えられるものが、働いている事業所内になにもない、商品・サービスにも特筆するものが一つも思い浮かばないのであれば、どんな営業をしても意味はないし、またあなたのいる事業所に未来もない。のこのこと出かけて行って頭を下げても、相手の仕事の邪魔をしに行っているようなもので、邪慳にされても仕方がない。
二つ目は、営業と連携との違いを理解することだ。
今の介護営業は、近隣の老健や病院、MSWやケアマネジャーをターゲットとしているが、ここはあくまで同業他社の地域の連携先であって営業先ではない。広義にとらえれば、関連業者との連携強化も営業活動の一つだと言えなくもないが、常識的に考えて、縁もゆかりも信頼関係もない、飛び込み営業の高齢者住宅にメリットがあるように、同業他社が無報酬で協力してくれるはずがないだろう。
同業他社と話をするときは「お願いします」ではなく、「今、困っていることはないか」「それをどのように協力して対応、解決できるのか」を聞くことからはじめよう。「介護人材不足」「食費や介護用品の原価の高騰」など、すべての介護サービス事業者は複数の困りごとを抱えている。高齢者住宅や介護施設の機能を使えば、「災害時の協力体制の構築」「ショート・ミドルなどの一時入居」「サービスエリアの調整」など、できることはたくさんあるはずだ。
そうすれば、その信頼関係、連携が「入居相談、理容相談」につながるかもしれない。
ただ、この同業他社との連携は管理者であっても個人でできることには限界があるし、その効果やメリットが生じるには、少し時間がかかる。事業者として、組織的、かつ長期的な視点をもって進めていかなければならない。
最後の一つは、関係先ではなく地域社会をターゲットにすることだ。
先に営業先と連携先は、違うことを述べた。
では、介護サービス事業が行うべき営業のターゲットとはどこか。
それは、地域社会や地域企業だ。
介護問題で困っているのは介護業界だけではない。いま、育児介護休業法の改正によって企業では、「介護離職防止」に向けての研修や対策が求められている。いまのところ、社会保険労務士などが、就業規則を見直したり、相談窓口を設置したりしているが、その多くが表面的な机上のものにとどまっている。
これから高齢者介護の問題は、要介護高齢者・家族だけではなく、介護離職によって企業の存続にかかわる問題に発展していく。介護離職の増加によって企業業績が悪化すれば、それは地域経済、地域産業、地域社会、自治体そののものの衰退に直結する。だから、介護は個人の問題ではなく、地域課題、社会課題なのだ。
介護休業制度は、親の介護をするための休業制度ではなく、「親の介護環境の整備」のための休業制度だ。経験豊富なケアマネジャーや社会福祉士が、企業や町内会や自治会に出向いて、親の介護の不安を抱える家族に対し、「介護のプロからみた介護休業」「認知症は早期発見できれば怖くない」「家族介護と上手く付き合うために」といった実践的な話ができれば、その営業効果は計り知れない。
以上、3つのポイントを挙げた。
営業というものは、ひとりの管理者が徒手空拳で、「お願いします、お願いします」と頭を下げて回ることではなく、その地域の中で、いかに信頼や存在意義を高めることができるか、信頼を勝ち取ることができるかを、中長期的に、かつ戦略的・組織的に行うものだということがわかるだろう。
それぞれの地域にある商工会議所、中小企業連合会などの経済団体や行政とも連携することも可能だろう。地場の企業と連携し、人事部を通して相談する体制が構築できれば、自分勝手な無理難題を言ってくる家族もいなくなる。地域の社会福祉協議会を通じて、町内会などで話をすれば、行政機関に貸しをつくることもできる。
信頼というブランディングを構築することが、営業の最終目的なのだ。
それほどお金がかかるものでも、手間がかかるものでもない。介護現場から飛び出して地域社会や企業に出向いて話をすることは、働く介護スタッフにとっても必ず良い効果をもたらすだろう。
できること、やるべきことは、まだまだたくさんあるはずだ。


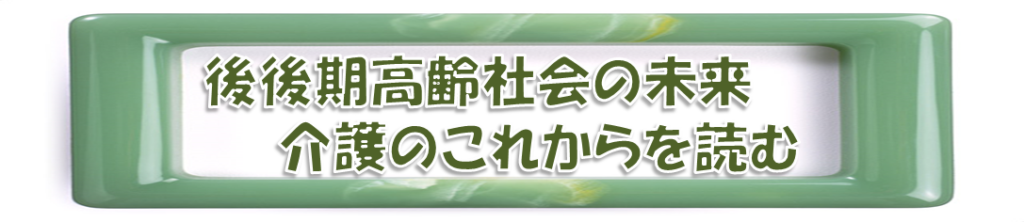
























この記事へのコメントはありません。