老人保健施設や病院、地域包括支援センター、ケアマネ事務所の知人、友人と話をしていると、よく話題になるのが、昨今の介護営業だ。わたしが介護の現場にいたころ(四半世紀前)も、近隣事業所への「新しいデイサービスができます。よろしくお願いします」という程度の挨拶まわりは行っていたが、介護事業者が「入居者、利用者を紹介してください」と、日常的に営業活動を行うなど考えもしなかった。京都市内だけでなく、遠方の大阪や滋賀県からやってくる管理者、事務長もいると言う。
その中心は高齢者住宅。本部からの一斉指示なのか、同じ系列の大手サ高住や介護付き有料老人ホームの違う管理者が、日に二人、三人と来ることもあり、ファックスで流れてくる「入居者紹介依頼」はその十数倍に及ぶ。
初めのころは「わざわざ来てもらったのだから…」「地域連携は重要だから…」と、仕事の手を止めて相談室で話を聞いていたというが、最近は、受付で名刺とパンフレットを置いて帰ってもらうだけになっている。
「自立から要支援、認知症高齢者・重度要介護高齢者でも対応可」
「保証人不要、生活保護可、申し込みの翌日には、入居可」
「一時金不要、月額費用〇〇万円(安さをアピール)」
そのいくつかを見せてもらったが、『安心、快適、なんでもOK、お願いします』だけで、それ以外の中身は何もない。訪問した証拠が必要なのか「お名刺下さい」と言われて困ると笑っていた。
いま、高齢者住宅の入居者確保は、「紹介業者頼み」になっている。
ただ紹介業者を通すと、一人当たり数十万円から百万円という紹介料を取られるため、それならば、事務長なり施設長が、地域のケアマネ事業所やMSW、老健施設などに頭を下げて回って、ひとりでも入居者を回してもらえば、その分、紹介料が浮くと考えているのだろう。
この紹介業者の中間搾取の問題は、「アゴダ」「トリバゴ」などのホテル業界も同じ。その値引き競争は、正当な価格競争・サービス競争を超え、その業界をむしばんでいくことが知られている。特に、高齢者住宅の紹介業は、宅建業法の抵触に加え(経産省はないと言い切っているが)、公的な介護報酬の一部が介護スタッフの待遇改善ではなく、紹介業に流れてしまうことが適切なのか…など、その課題は大きい。また、そのビジネスモデルは、不動産仲介業とは全く別の営業のアウトソーシングであり、利用する高齢者・家族にも中立・公平ではないことを隠して、紹介を行うことはコンプライアンス的にも大きな問題があるだろう。逆に、もし民間の紹介業を認めるのであれば、居宅介護支援や病院や老健にも、介護報酬外の紹介料の請求を認めるべきだし、そうすれば、そこに一定の責任と専門性が加味されるため、紹介の質も向上すると思うのだがそれは介護保険法で禁止されている。
なぜこのようなダブルスタンダードになるのかと言えば、厚労省・経済産業省は省庁間の利権をすみ分けし、利用者の利便性や制度の安定よりも、「インターネットを使った新ビジネス」「新しい天下り団体を作って天下る」ということしか考えていないからだ。結果、業界団体を立ち上げさせ「業界の自主規制に委ねる」とするだけで、まったく規制には動いていない。これは、人材紹介や人材派遣も同じことが言える。実業を行う事業者を蔑ろにして、中抜きビジネスを優遇すると、そちらに人材やお金が流れ、ホテル業や介護サービス業そのものが萎んでいくのは自明の理だ。こんなことを続けていれば、サービスが劣化し、待遇が改善されないまま介護人材が逃げていくのは当然だろう。
厚労省や国交省は、将来的にはすべての介護人材確保、入居者確保は紹介ビジネス通させるつもりなのだろうか。「社会保障に基づく医療介護」だけを締め付け、中間搾取のビジネスを儲けさせるという仕組みを行政主導でやっているというのが、日本の社会保障が崩壊していく一つの大きな要因だ。厚労省をはじめ国は介護が崩壊しても、紹介ビジネスが残ればよいと思っているのだろう。
のっけから話が逸れたので、高齢者介護の営業活動に話を戻そう。
大手高齢者住宅の中には、「管理者の仕事は入居者確保、営業活動だ」と考えている経営者が多いようだが、「目先の利益しか頭にないんだなぁ…」「介護職員や介護現場のことを何も考えていないんだぁ…」と、このような無意味な営業活動をさせられる施設長・管理者、そこで働いている介護スタッフを、心底気の毒に思う。
こんなものは営業活動でも何でもない。営業の基本は広報活動であり、そのカウンターパート(相手方)にとって有益な商品・情報を提供することを目的としているが、伝えることも、売るものもないまま、へこへこと頭を下げてお願いに回る、いわゆる「乞食営業」(はなはだ不適切な表現で申し訳ないが…)でしかないからだ。
無意味な介護営業が引き起こす人材流出
病院や老健からの入居者紹介はゼロではないため、このような介護営業が続けられているのだろう。ただ、ケアマネジャーやMSWは、処遇しやすい穏やかな高齢者や常識的な家族を、このような飛び込み営業の高齢者住宅に紹介することはない。自己のグループ内、または周囲の質の高い高齢者住宅や、つながりのある特養ホームなどへの入所調整を優先するからだ。
そのパンフレットは、「紹介するわけではありませんが…、(自己責任で)こんなところにも話を聞いてみればいかがでしょう…」と無関係をアピールすることを前提として、周辺症状など対応の難しい認知症高齢者や、感情的で暴言などトラブルの多い高齢者、「どこでもいいから早く見つけろ」と無理難題を言ってくる家族に渡る。
その間接的な紹介を受けた高齢者住宅は、「誰でもOK、すぐに入居可」と営業しているため、どんな要介護状態の高齢者、家族でも受け入れざるを得ない。一度断ると、二度と紹介してもらえなくなるからだ。「ありがとうございます。すぐに対応いたします」と、ペコペコと頭を下げて、難しい高齢者、家族を受け入れることになる。
大変なのは、受け入れる側の介護現場だ。必要最低限のアセスメントさえ行わず、受け入れ準備をしないまま、「昨日契約」「今日の入所」で、対応の難しい高齢者、家族が入ってくるからだ。こんな乱暴な話はない。
このような営業活動をさせているのは、管理者本人ではなく、会社の経営陣なのだが、介護現場の怒りは、その管理者に向けられる。「どうして、こんな難しい入居者を突然、受け入れてくるのか」「なぜ、事前に現場に連絡や相談がないのか」と反発されても、管理者は「お願いします。お願いします」と頭を下げるしかない。トラブルや事故のリスク、クレーマー家族が増えるのに対し、「こんな管理者、ホーム長の下では働けない」」とまともな介護スタッフ、ケアマネジャーはどんどん減っていく。「言われたことしかやらない」「事故やトラブルも無関心」という人材派遣や短期バイトばかりになって、人件費アップに反比例してサービスの質は更にダウンする。そして、最後には、その管理者・ホーム長からの退職届が本部に送付されてくるという流れだ。
【介護営業がもたらす人材流出】
① 場当たり的な介護営業では、対応の難しい高齢者、家族しか紹介されない
② アセスメントもないまま受け入れ、事故やトラブルのリスクが増大する
③ 介護現場への不満が管理者に集中、中核となる優秀な介護人材の流出
④ 最後は、管理者、ホーム長が、辞めてしまう
大手高齢者住宅の経営者は、「管理者になりたい人がいない」と嘆くが、当たり前のことだ。
一時期、大手高齢者住宅が業務拡大のために、「経験5年以上・介護福祉士・介護福祉士・ケアマネ資格者」を対象に管理職(施設長)を大募集したことがある。「いまより給与があがる」とつられて、特養ホームから転職した介護スタッフも多いと聞くが、そのほとんどは残っていない。
「高齢者に、いい介護をしたい」「社会の役に立つ仕事がしたい」と、介護業界に入ってきた人間が、高齢者からも家族からも文句を言われ、スタッフからも責められて、「お願いします、お願いします」「すいません、すいません」と、頭を下げるだけの仕事をやりたいなどと思うはずがない。
介護保険制度の発足で、それまで老人福祉に限定されていた高齢者介護が、営利事業者に開放された最大の理由は、「営利事業者、一般事業者の創意工夫を介護業界に取り入れるため」だったが、実際は、目先の利益しか追及しない素人経営者ばかりが算入し、不正請求や過重労働など「営利企業のダメなところばかりが入ってきた」というのが現実だろう。従来の社会福祉法人や医療法人も「医療、介護も経営の時代だ」と、その営利法人に盲目的に追従するため、業界はどんどん悪いほうに向かっていく。
介護現場で、高齢者を笑わせ、家族からの信頼も厚く、きらきらと輝いていた有為な介護人材を、無理に管理職に登用して、すりつぶしていくのが、今の介護業界だといっても過言ではない。
そんな企業、業界に未来があるはずがないだろう。
>>>介護営業のありかた (後) ~介護営業のターゲットとその目的~


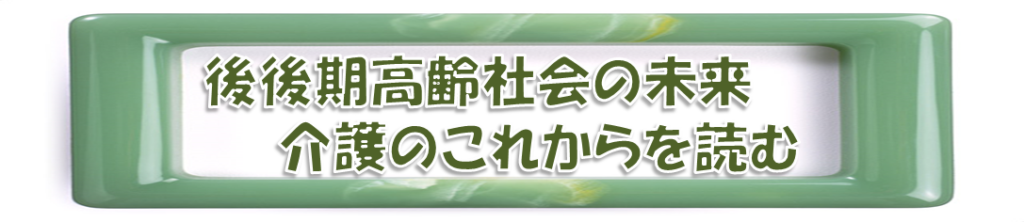
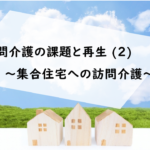























この記事へのコメントはありません。