介護休業制度の取得事例 Ⅱ ~脳梗塞から老人ホーム~(上) 🔗 >>>から続く
ここでは、介護休業制度の実際の取得例について、解説しています。
前回に引き続いて、骨折や脳梗塞などで突然入院し、その後のリハビリで、自宅に戻ることを検討したけれど、老人ホームに入所することを決めたというケースについて解説します。
父の退院、介護休業の取得
手術をした病院で四週間程度、そこからリハビリ病院に一ヶ月半ほど入院しました。
どちらの病院でも、MSWさん(医療相談員さん)にもお世話になりました。
その間、毎週、水曜日と土曜日を休みにしてもらい、忙しくて行けない時には、兄や兄嫁、甥姪が代わりに行ってくれました。車いす生活になるといわれていましたが、リハビリを頑張ってくれた結果、左半身に麻痺が残ったものの、何とか自立歩行(杖歩行)と自立排泄(立ち座りがまだ少し不安定)ができるまでに回復し、要介護二と判定されました。リハビリ病院からの紹介でケアマネジャーさんも決まり、介護ベッドや手すりの設置、一日二回の訪問介護(調理・洗濯、入浴など)、週一回の訪問リハビリ(入浴)、週一回の訪問看護をお願いすることにしました。
父の退院に合わせて、私も、二ヶ月の介護休業をいただくことになりました。
入院中は、「仕事はどうなっている?」「そんなに何度も来て大丈夫か?」「何度も来なくていいぞ」と心配してくれたのですが、やはり退院後のことが心配だったようで、「お父さんの退院に合わせて、二ヶ月お休みをいただいたから…」と言うと少し驚いたようでしたが、気丈な父が麻痺した口で「すまんなお前に迷惑かけて…」と涙ぐみ、私も一緒に泣いてしまいました。
退院の三日前からお休みをいただき、ケアマネジャーさんとの調整、ケアカンファレンス、住宅改修(手すりの設置)などを行いました。
智子さんからも、介護休業の取得にあたって二つのアドバイスをいただきました。
一つは、介護休業は私が介護をする期間ではなく、介護休業後の生活を考えて、介護環境を整える期間だということです。
「介護休業は二ヶ月」ということを念頭に置いて、その間に、その後のこと(自宅で生活し続けるのか、その課題は何か、できない場合どうするのか)について考え、想定し、覚悟しなければなりません。介護休業の二ヶ月満了が近くなってから「一人ではやっぱり心配」「独居は難しいかな」にしてはいけないということです。介護休業中は、父が一人になった時に問題がないかをチェックするのが家族の役割で、買い物や調理をお願いしているヘルパーさんの仕事に手を出さないようにと言われました。
もう一つは、私の意向をきちんと父と兄達に伝えるということです。
子供が三人いる場合、「介護負担はそれぞれ1/3ずつ協力し合って…」というのは理想だけれど、それぞれの生活状況や物理的距離などによって、現実的にそのようなケースはほとんどないと言われました。
今回の場合、私が中心になって介護を行うことになるため、兄達には自分の考えや方針をきちんと伝え、金銭的な支援などできることを依頼するとともに、決めた方針に対して、あれこれ口を出さないようにさせることも大切だと言われました。ごちゃごちゃ言うなら、任せるから全部そっちでやってくれ(怒)と時には切れることも必要と笑いながら言われました(幸い、そんなことにはなりませんでしたが…)。
父が自宅に戻ってきた翌日、父、二人の兄と兄嫁、私の六人でこれからのことについて話し合いました。
「介護休業は二ヶ月しか取れない、仕事を辞めるつもりはない」といった私に、一番共感してくれたのは長兄の兄嫁でした。「あなたにばかり負担をかけて申し訳ないと思っている。仕事を辞めるなんてとんでもない。私もできる限りのことはさせてもらう」と言ってくれました。次兄の兄嫁も土日には子供と一緒に来てくれるというので、その場で一ヶ月分のスケジュールを決めることができ、五人でラインを交換し、父の情報を共有することにしました。
介護休業をいただいたおかげで、一変通りの親戚づきあいしかなかった兄嫁や姪甥たちとも仲良くすることができ、また父も、私の料理を美味しいと食べてくれ、二人で晩酌をしたり、昔話をしたりして、子供の頃は「お父さん大好きの父親っ子」だったことを思い出しました。
介護不安、老人ホームの検討
ただ、その一方で、実際に実家での生活がスタートし、一週間、10日たつと、日によって歩行中にふらついたり、トイレで立ち上がる時に転倒したこともあり、「二ヶ月後に本当に一人で生活することができるのか…」という不安が大きくなりました。「介護休業生活はどうですか?」とお電話いただいた智子さんに、その不安を相談すると、「介護サービスの変更は可能だが、本人も家族も一定の覚悟は必要」「もしくは、老人ホームや高齢者住宅を探してみれば良いのでは」と提案されました。
父は要介護二であり、特養ホームはまだ対象外です。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅も考えないことはなかったのですが、父が納得するか疑問でしたし、また数年前に亡くなった伯母(母の姉)が入所していた四人部屋の特養ホームは、寝たきりや認知症の人ばかりだったこともあり、躊躇していました。
しかし、民間の高齢者住宅は、全室個室であることや、父と同程度の要介護状態の高齢者も多いということでした。また老人ホームに入るというのは、「子供の家の近くのアパートに住みかえる」「たまたまそのアパートに介助機能が付いていた」という程度のことでしかなく、「京都で探せば、仕事終わりに、毎日会いに行けるじゃない」と言われました
ただ大切なことは、押し付けてはいけないということ。 子供のできることは限られていること、リスクも含めて最後の選択はお父さんがすることが大切だと教えてもらいました。そうしないと老人ホームに入っても親子共に幸せにはなれないと…。
その話を兄や兄嫁達にすると、「そっちの方が良いと思う」とみんな賛成してくれました。
夕食でお酒を飲んでいるときに、父にその話をすると「そうだなぁ…」と考え込んでいましたが、「そっちの方がいいかもなぁ…」と了承してくれました。そこではまだ「老人ホームに決定」ではなく、金額やサービス内容もあるので、資料を取り寄せたり、見学にいったりして「良いところが見つかれば…」ということにしました。
その日から、「京都近郊(私が通えるところ)」「入居一時金が数千万円じゃないところ」「介護が充実しているところ」とターゲットを絞って探し始めました。民間の高齢者住宅は、介護付有料老人ホームだけでなく、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など様々な種類があり、みんな「介護が必要になっても安心・快適」と書いてあります。ただ、現在要介護二であることや、将来、脳梗塞等が再発して介護が重くなったときのことを考えると「介護付が良いのでは…」というアドバイスを受け、最終的に五つくらいの介護付有料老人ホームに絞り込んで見学し、うち二つのホームは、父も一緒に見学にいきました。
一ヶ月くらいかけて、じっくりと選んだ結果、入居一時金がないこともあり月額費用が少し高いのですが、施設長さんが介護福祉士さんで、スタッフの方も感じが良く、介護機能の整ったところに決めました。月額費用だけでなく医療費などその他生活費を含めると、父の年金では月に一〇万円ほど不足するので、その分は父の預貯金から取り崩すことにしました。兄たちには、足りなくなった時にお願いすること、できるだけ父に面会に来てやってほしいと伝えました。
「新しい生活に慣れるだろうか」と心配していたのですが、スタッフの皆さんにもよくしていただいて、他の入居者の方と将棋をしたりカラオケをしたりと、家にいるときよりも元気になりました。最初の頃は毎日、面会にいっていたのですが、「そんな毎日来なくてよい」と言われ、「来週は忙しいから来れないよ」とか「取材で近くまで行ったので父の部屋でコーヒー休憩」とお互いに新しい生活になじんできました。
父が倒れたという電話を受けてから、介護休業・老人ホームへの入居まで怒涛のような三ヶ月でしたが、今から思うと楽しい三ヶ月であり、感謝した三ヶ月であり、そしてたくさん泣いた三ケ月でした。「わたしの人生、これで終わりか」と思ったこともありました。
半年が経過し、それまでと同じように仕事をしていますが、社長や編集長、私の穴を埋めてくれた他のスタッフの皆さん、そして智子さん、その他たくさんの人に本当に感謝しています。今までより会社やみんなの力になれるよう、これからも仕事を頑張りたいと思っています。
>>>>新連載 介護離職をしない、させない社会へ (TOP)

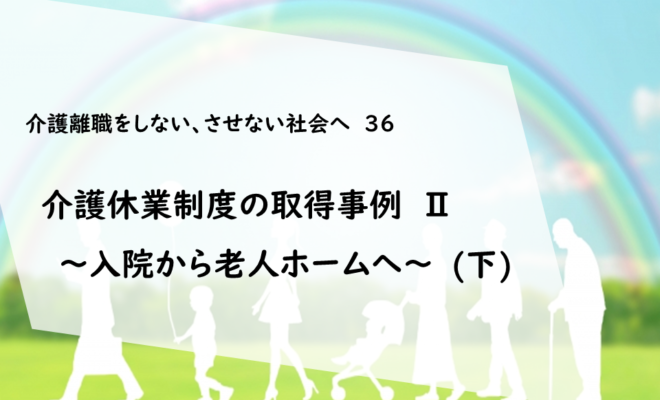




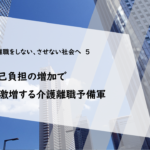

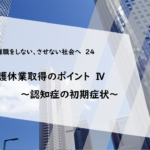









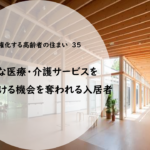








この記事へのコメントはありません。