ここでは、介護休業制度の実際の取得例について、解説しています。
今回は、骨折や脳梗塞ではなく、老人性うつ病と診断された一人暮らしの母親への支援の事例について解説します。
介 護 問 題 の 発 生
私は五二歳、とある金融機関に勤めています。
家族は妻と大学生の長女、高校生の次女の四人家族で、都内のマンションに暮らしています。
実家は、車で一時間ほどのところにあり、八〇歳の母が一人で生活しています。一週間に一度程度は電話をし、月に一度程度は実家に帰っていました。体操教室に行ったり、趣味のパッチワークをしたりと、元気に暮らしていたのですが、ここ一ヶ月程度、やせてきたのが気になりました。話を聞くと「ご飯がおいしくない」と言い、体操教室も休んでいる様子。また「買い物に行っても、何を買うのか忘れる」「人の顔や名前が思い出せない」とも言い、薬の飲み忘れも増えているとのことでした。
同じく一時間程度のところに住んでいる妹に相談すると「認知症の初期症状ではないか…」と言われ、本人も少し気になっているようでしたので、有給をとって老年科の受診をすることにしました。そうすると、「老人性うつ」と診断されました。そこで「一日一食しか食べないことがある」「家の中で何度も転倒している」「ガスコンロを消し忘れ鍋を焦がしたことがある」「テレビも見ないで、ぼーっとしていることが多い」と初めて知りました。
それを妹に話すと、介護保険サービスを利用するか否かは別にして「要介護認定をしておいたほうが良いのでは…」と言われました。「介護ではなくて病気だろう…」「うつ病が治れば解決するだろう」と思ったのですが、うつ病に限らず、高齢期に病気になると「要介護」に可能性が高いため、その方面からの支援も考えるべきだと言われました。
とりあえず、地域包括支援センターに連絡し、要介護認定をお願いすることにしました。要介護認定は「要介護一」と判定されました。その間は、私たち夫婦だけでなく、妹や子供達も泊まりにいってくれたので、少し元気になったようでした。
ただ、一つ心配がありました。
私は勤めていた金融機関から出向する年代に差し掛かっており、ある会社(A社)から「来ないか」と誘いを受けています。まだ半年先の話なのですが、私のこれまで金融機関で培った経験やノウハウを十分に生かせる職場ですし、ありがたいことに給与もあまり下がりません。長女は来年大学を卒業し、次女も大学へ進学し一人暮らしを始めるということも重なり、いま住んでいるマンションを引き払い、夫婦で移り住む予定にしていました。
しかし、その会社がある場所から実家までは、電車でも四時間程度の時間がかかり、今のようにそうそう頻繁に通うことはできません。妹も義弟の父の介護を抱えており、同居することも介護をすることもできません。母のことを考えると、「願ってもない話だけれど、転職(出向)は断った方が良いのだろうか…」「今のマンションから通える場所が良いか…」「実家に帰ってそこから通える場所が良いだろうか…」と、考え込んでしまいました。
上 司 ・ 人 事 に 相 談
一週間ほど悩んだ結果、先方にも迷惑が掛かるので現状を伝えておいた方が良いと思い、答えがでないまま上司に相談することにしました
やはり、私だけでなく同年代の「親の介護」に関する相談は増えていると言います。「A社への出向の話は人事にも通っている話であるし、介護の問題も含め人事部に相談してみては…」と言われ、翌日アポイントを取って本店の人事部に向かうことにしました。
人事担当者に現在の状況について、簡単に話をしました。
◆ 来年の春に出向を予定(A社)しており、転居する予定であった
◆ 母が、軽度の「老人性うつ」になり、認知症や将来の要介護を心配している
◆ 要介護認定を行い、要介護1と判定された。
◆ 現在のマンションからは一時間程度だが、転職・転居すると四時間くらいかかる
◆ 転居後の母の生活が心配である(認知症や要介護状態が進むのではないか)
◆ A社への出向を進めるべきか、断るべきか悩んでいる
話の結果、「A社を断るか否かをすぐに決断する必要はなく、まず母の介護への対応を検討するのが良い」ということになりました。そこに同席していたのは「介護担当相談員」の森下さんという女性で、人事担当者は「介護の問題は森下さんと…」と言うと部屋をでていきました。
私は、「介護の問題」ではなく、「出向の問題」を相談に来たつもりだったのですが、森下さんの話によると、私と同じように介護の問題で出向を取りやめたり、転勤を断ったり、また早期離職を検討するというケースが増えているため、人事部の中に介護問題の相談を専門に受け持つ担当者を作ったとのことでした。
彼女はもともと銀行員ではなく、介護福祉士とケアマネジャーの資格を持っており、介護現場の相談経験も豊富だと言うことで、「自分だけでなく、みんな介護で悩んでいるんだなぁ」とあらためて認識するとともに、銀行が積極的にバックアップしてくれていることが心強くもありました。「プライベートな情報については秘密厳守します。人事にも反映されません」と森下さんが言ってくれたこともあり、安心して母の病状や妹のこと、また不安に思っていることなどについて相談することができました。
介護休業の取得事例 Ⅲ ~老人性うつ病と診断された母~ (下) へ続く
>>>>新連載 介護離職をしない、させない社会へ (TOP)

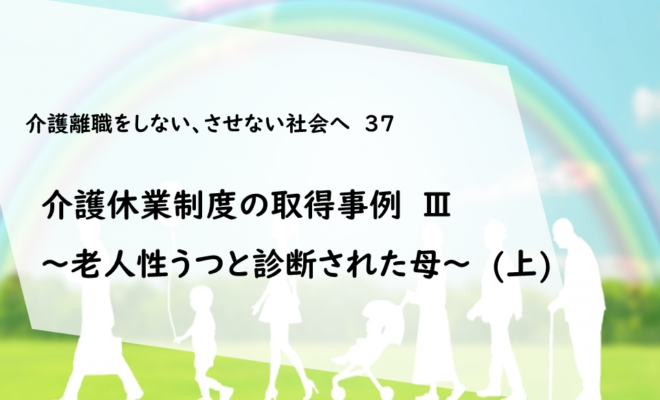




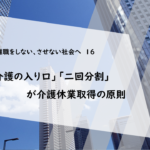
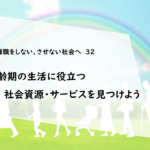

















この記事へのコメントはありません。