政府は、過疎地などで高齢者らが安心して暮らせる住まいを確保するため、低料金で入居できるシェアハウスを全国的に整備する方針だ。年内に詳細を詰め、今後3年間で100カ所を目指す。介護など地域ケアの提供拠点とも位置付ける。地方では、既存の介護施設の維持が危ぶまれており、住まいを失いかねない高齢者への対応が急務となっている。人口減少に対処する地方創生につながる新たな取り組みとして、自治体側は歓迎している。
政府、高齢者シェアハウス整備へ 介護も提供、3年間で100カ所 (共同通信) 🔗
政府は、特養ホームなどの介護保険施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に加えて、高齢者向けのシェアハウスを制度化し、整備するらしい。
シェアハウスというのは、リビング、キッチン、バスルーム、トイレなどは共同で利用し、各入居者には個室が割り当てられるというタイプのものだ。今の段階では、分かっていることは少ないけれど、「小規模」「低価格化」「既存の小規模の介護施設との併設」ということらしい。イメージとしては、定員は10人程度、10万円前半というところだろうか。
高齢期のシェアハウスを全否定をするわけではない。わたしも80歳、85歳になれば、気心の知れた友人・知人と、シェアハウスで楽しく暮らすのも良いかと思うからだ。有料老人ホームやサ高住などの建物関連の規制撤廃を想定しているのだろうと思う。
ただ、これは個人でやりたいと考えるのと、ビジネスモデルに乗るかという話は別だ。コメントには、大学教授や介護ジャーナリストなどの、いわゆる識者ももろ手を挙げて「素晴らしい」と賛同しているが、それが正しい、正しくないというよりも、どのような対象者、事業モデルを想定しているのか、さっぱりと見えてこないからだ。
① 価格設定について
まず、理解しておかなければならないことは、高齢者の住まいを考えるにあたって、「小規模化」と「低価格化」は反比例するということだ。それは認知症グループホームや地域密着型特養ホームを見ればわかる。高齢者、特に、要介護高齢者を対象とする場合、階段は使えないので、リビング・キッチン・バスルーム・トイレ、そして入居定員10人の独居高齢者・夫婦世帯が、各居室が一つのフロア(一階部分)に集約されることになる。かなりの敷地面積が必要となるため、奇特な大地主が土地を無償提供してくれない限り、都市部では難しい。
では、地方の田舎の自治体ではどうだろう。
記事によれば、田舎の地方都市を想定しているものと思われる。農家などの既存の大きな建物を改築することになるだろうが、古い日本家屋は段差、敷居が多く、廊下幅なども狭いことや、すき間が多く寒暖差が激しいことから高齢者には適していない。特に、車いす利用を想定するとなると、基礎まで見直す必要があるし、リビングも相当の広さが必要となる。浴室も機械浴までは必要なくても、高齢者仕様・介助ができる十分な広さが必要となるし、トイレも車椅子でも利用できる広さ、それも10名定員であれば二つは必要となる。そうなれば、給水・排水管まで見直す必要がある。改築でも新築と同じくらいお金がかかるだろう。 改修費の費用の一部を財政支援するとしているが、最大でもサ高住と同程度、一人当たり100万円くらいだろう。20年償却とすれば、2000円~2500円程度にしかならない。
高齢者が10人程度が入居できるシェアハウスを作るとなると、土地がゼロに近いとしても、また社会福祉法人、NPOなどで税制優遇や補助金をもらっても、改築でどんな安く仕上げても5万円未満ということはあり得ない。新築の場合、六畳一間の単身者でも七万円~八万円、夫婦だと十万円にはなるだろう。
若者のシェアハウスが安いのは、ファミリータイプの既存の一軒家・マンションをそのままシェアできるからだ。
軽度であっても、要介護高齢者に対応するには一つのフロアに住居部分を集約する必要があり、車椅子仕様の広いリビング、トイレ、浴室に改築しようとすれば、その対象エリア、対象物件はかなり限られ、それほど安くはならない。
② 対象者について
家賃だけで、六畳一間の単身者でも七万円~八万円、夫婦だと十万円とすると、そこに食事代や共益費などの共益費を加えると、介護医療を受けていない人でも、単身者15万円前後、夫婦では20万円を超えるだろう。軽度要介護でも、介護医療費を加えると、単身者でも20万円超、夫婦だと25万円をこえる。政府が「低価格」と言っているのが、いくらを想定しているのかわからないが、自立~要支援高齢者を対象とするのであれば、サ高住の価格設定とほとんど変わらない。サ高住をシェアハウスにしたからといって、建築費や食費が安くなることはない。当たり前のことだ。
いまの高齢者の半数は、月額年金10万円以下。これから高齢者に入る氷河期世代やすでに後期高齢者になっているリストラ世代は、年金額も少なく、預貯金もないため、その対象にはならない。
では、その価格の支払い可能な高齢者は、シェアハウスを選ぶのだろうか。
高齢期になってからシェアハウスが良いと思うのは、それぞれに性格・気心の知れれた、気兼ねなく生活できる友人・知人ばかりであることが前提だ。若者と比べて、高齢期になると、それまでの人生によって、生活リズムや生活環境は全く違うし、それまで一人暮らしだった人が、他人に合わせることはむずかしい。不特定多数の募集で、どんな人かもわからないのに、男女混合で、認知機能が低下した人も、要介護の人もいる中に、トイレや浴室、キッチン、リビングなどを共有するシェアハウスに入りたいと思うだろうか。サ高住などと違って、逃げる場所もないし、部屋に鍵がつけられたとしても、プライバシーも不十分で、怒鳴り声や電話の声、テレビの大きな音もそのまま聞こえる。「孤独の解消に役立つ」などと変なことをいう人もいるようだが、どんなに寂しくても、普通の人はこんなトラブル・リスクの高いところには住み替えない。
③ 運用・運営について
最大の問題は、事業者の運営や運用、その責任だ。
自立高齢者~要介護高齢者を対象としていると言うが、高齢者の住まいは、その対象が広がれば広がるほど、多様なニーズに対応しなければならないため運営が難しい。また、「要介護高齢者」より「自立~要支援のほうが対応が簡単」だと考える人が多いがそれは正反対だ。「元気な居住者は施設の業務を手伝える」と安易に考えているようだが、自立度の高い高齢者が多くなれば、それだけ人間関係や音、ルールなどを巡ってトラブルになりやすい。少人数であれば、あるほど、そのトラブルの密度は高くなる。自立度の高い見知らぬ高齢者同士が、一つの家をシェアして暮らすなどというのは、根本的に高齢者の生活特性や、その住まい事業のリスクを知らなすぎる。
こんなものが運営できるかと言えば、絶対にできない。
夜間はどうするのだろう。10人~15人に夜勤一人をつけるというのであれば、それだけで月額費用は、一人当たり5万円以上あがる。小規模の介護施設の併設などと言っているが、そこにいるスタッフが、このシェアハウスの高齢者の面倒をみるということだろうか。認知症の人は、このようなシェアハウスでは生活できないが、途中で認知症になった人には、誰が退居を求めるのだろう。本人は、とても理解・納得しないだろうが、強制的に排除できるのだろうか。
また、純粋に不動産賃貸ビジネスに特化するとしても、10人程度のシェアハウスだと、一人、二人でも空所ができれば、それだけで赤字になる。初めから20人以上の希望者がいて、その中で事前に何度も顔合わせをして、ルール作りをして、仲良くなって…みたいなことをしなければトラブルが多発することになるし、そんなことをすればとても低価格にできない。
「建物は既存の介護施設の転用や一部活用で賄う」「子どもの居場所など、地域住民が集う場としても期待する」「福祉人材が集約されるため、サービス提供の効率化も見込む」などと、適当なことを言っているが、そもそも価格・対象・運用、どれ一つをとっても事業として成り立つはずがないのだ。
いや、一つだけ、ビジネスモデルに乗せる方法がある。
それは、いまのサービス付き高齢者向け住宅と同じだ。
サ高住は、高専賃の流れをくむものであり、「一般のマンション・アパートは高齢者お断りなので、自宅で生活できない自立・要支援高齢者向けの賃貸住宅を」という触れ込みで整備されたのだが、その当初の役割は、誰も記憶にさえないほど遠くに追いやられ、その大半は「要介護・認知症高齢者の囲い込み住宅」となっている。それは、そもそも自立~要支援高齢者の住宅ニーズは「要介護向け住宅」と比べて緊急性が低いからだ。ここは不正の温床となっており、住宅型有料老人ホーム、ナーシングホームを合わせると、そこで、搾取される無駄な医療介護費は、年間二兆~三兆円規模になる。
このシェアハウスも必ず同じことになる。
それ以外に、事業性が確保できるビジネスモデルはないからだ。つまり、その制度矛盾を突いた、その二匹目のどじょうを狙っている人達がいるということだ。
その主体となるのは誰か。地方都市にある小規模の診療所だ。 彼らは50人規模のサービス付き高齢者向け住宅を整備する財力も冒険心もないが、訪問介護を併設した診療所のとなりに、10人~15人規模のシェアハウスを整備し、「自宅だから」と寝たきり高齢者を集めて訪問診療・訪問看護を利用させれば、巨額の医療介護費を受け取ることができる。有床診療所は採算が合わないが、シェアハウスにすれば利益幅は大きい。経管栄養や胃瘻などであれば、食事介助も必要なく、排泄も定期的なオムツ介助だけ。入浴設備も清拭にすれば、人もいらないし、特別な機能も必要ない。
厚労省も、はじめからそのつもりなのだ。そう考えれば、「自治体からの要請」「人口減少に対処する地方創生」などと大仰に構えてはいるが、実際は、その陰でだれが要請しているかわかるだろう。
専門家によれば、多様な高齢期の住まいの在り方が重要だということだが、多様な住まいを選ぶ選択肢などどこにもない。あるのは、「運が良いか悪いか」「損か得か」だけだ。いまでさえ、「介護と福祉の混乱」「囲い込み」などの制度の混乱、巨額の不正搾取さえ整理できていないのに、こんなものを作っても、その混沌や不公平感を加速させるだけだ。
一般の人たちが、「歳をとれば、シェアハウスもいいね」と空想するのは良いけれど、いまの介護や高齢者の住まいの現状をみれば、とても「多様性」などというふざけた言葉がでてくるはずがない。
これくらいのことは、介護の現場、高齢者の住まいのことを少しでも知っていれば、すぐにわかることだ。
今、参議院議員選挙の真っ最中だが、厚労省や自民党は国民をバカにしすぎだ(他の政党も変わらないが)。貢いでくれる医師会の言いなりで、天下り先を作ることだけに心血を注ぐのではなく、地に足をつけて、後後期高齢社会の介護医療制度の公平性や持続性を考えるべきではないか。
そんな当たり前のことを政治家や官僚に望むのも難しいのだろうか。


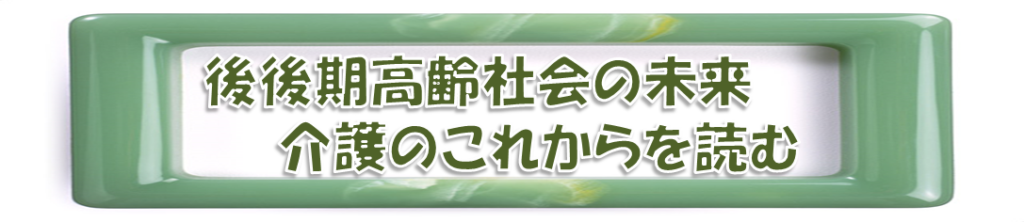






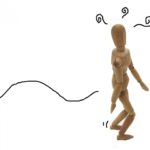









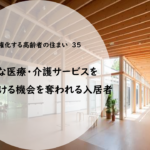








この記事へのコメントはありません。