厚労省は、2024年の訪問介護の介護報酬引き下げの理由として、「訪問介護は、他の介護サービス事業の平均(2.4%)と比較して、顕著に利益率が高い(7.8%)」ということを上げているが、この数字にはまったく意味がない。それは、前回の「高齢者住宅の囲い込み」だけでなく、「社会福祉法人と営利法人の運営格差」、更には、住宅密集地と集落点在などの地域特性によっても、経営環境・ビジネスモデルの土台が根本的に違うため、「平均利益率」という考え方自体がナンセンスなのだ。
言い換えれば、それは訪問介護の仕組みの土台そのものが凸凹で不安定であることを示している。
ここでは、現在の訪問介護サービス事業の再構築、立て直しのために避けては通れない根本的な課題とその解決策について考える。最終回は、「社会福祉法人の経営格差」と「移動時間の報酬算定」について。
社会福祉法人と民間営利事業の経営格差をどうするか
三つ目の課題は、社会福祉法人と民間事業者が行っている訪問介護の経営格差をどのように、整理・統合していくのかだ。第二種社会福祉事業においては、同じ訪問介護、通所介護でも、社会福祉法人は、法人税、事業税などが非課税となることや、特に特養ホームに訪問介護サービス事業所が併設されている場合、運営費・事務費の按分ができるため、運営格差はより大きくなる。
地域経済、自治体の財政から見ると、介護サービス事業は営利事業であるため、利益が出た分は、事業税や法人住民税などで還元してもらうことが可能だが、社会福祉法人の場合は、高い利益がでてもその収益の社会還元ができないことを意味している。
ただ、これは「運営格差はケシカラン」という単純な話ではない。
この問題については、【社会福祉法人は冬の時代を迎える (Ⅱ) ~優遇施策の見直し~🔗】でも詳しく述べているため、是非お読みいただきたいが、その改善に向けた論点は三つある。
① 第二種社会福祉事業に対する運営格差の見直し
② 社会福祉法人に対する第二種社会福祉事業の役割の明確化
③ 採算性の低い地域での介護サービスの実施
この中で、特に重要だと考えているのが、②の社会福祉法人の役割の明確化だ。今後、少子化の中で独居の認知症高齢者、重度要介護・認知症の夫婦など、通常の訪問介護だけでは、対応できない難しいケースが激増することになる。社会福祉法人の役割は、このような困難ケース・福祉ケースに対応することであり、その支援体制の強化は不可欠だ。
社会福祉法人は、地域住民に対する「親の介護勉強会」、企業向けの「介護離職防止」に向けた講演会の実施など、より積極的に地域の介護・福祉課題に取り組む必要がある。
更に今後は、訪問介護の「零細事業者への統合・吸収」などの支援、また「囲い込みへの規制強化」に伴う、入居者支援なども視野に入ってくるだろう。社会福祉法人には、その地域の介護・福祉の基礎としての、ノウハウ・体力が求められるということだ。社会福祉というぬるま湯につかりながら、営利企業と同程度のサービスしか提供できないような社会福祉法人には存在意義はない。
訪問介護の「移動時間」の報酬算定をどう考えるか
最後の課題は、訪問介護の移動時間の報酬算定をどう考えるのかだ。
これは、上記③で挙げた、採算性の低い地域での介護サービスの実施の問題と深くかかわっている。そのため、東京・大阪のような密集地など、どの地域・エリアでも、移動時間・手待ち時間の報酬算定を認めよという話ではない。ただ、往復一時間以上かけて離れた集落に訪問介護に出向く必要があるのに、介護報酬算定が、「介護時間しか算定できない」というのでは、現実的に不可能だ。
そのためにも必要だと考えているのが、介護のコンパクトシティ構想だ。
その論点は二つある。
① エリア単位での介護サービス利用の限定
市街地から離れた数件程度の家しかない集落に、電気・水道・道路などの公共インフラを整備し続けるというのは現実的ではない。これは介護サービスも同じ。離れたA地区、B地区、C地区に分散している個別の家を個別に訪問する場合、移動ばかりで、一日に数人しか介護できないため、採算がとれない。限られた介護資源を効率的に運用するには、A地区の訪問看護は月曜日、B地区の訪問入浴は火曜日など、地域によって介護サービスを限定するしかない。
② エリア単位での介護サービスの停止
全国どこに住んでいても、自由に複数の種類の介護サービスを、いつでも受けられるというシステムは維持できない。特に、最寄りの介護サービス事業所から車で一時間離れたエリアで暮らす重度要介護高齢者に、一日に何度も訪問して介護するということは現実的ではない。そのため、「デイサービスしか利用できない」「訪問看護対象外のエリア」など「介護サービスが提供できない地域・エリア」を指定すると同時に、包括的な介護が必要となる重度要介護高齢者は、介護機能の整った地域や高齢者住宅に移り住んでもらう必要がでてくる。
この介護のコンパクトシティ構想は、拙著、「地域包括ケアの落とし穴」 (花伝社) に詳しく述べているので、是非お読みいただきたいが、簡単にいえば、濃淡を決めて戦略的に地域包括ケアシステムを縮小させていくというものだ。民間企業は「採算が取れない地域のサービスはやらない」となるのは当然のことだし、「非営利だから」と社会福祉法人にその負担をすべて負わせるにも限界がある。
そのため、各自治体が、地域包括ケアシステムの中で、これらの政策を一体的に行うことを前提に、それでも「離れた集落に訪問介護に行く必要がある」というケースに限り、移動時間を介護報酬、または自治体独自の単費での支援を行うべきだと考えている。これも、「離れた地域への訪問介護が大変だ」「だから、移動時間も報酬算定すべき」という単純な話ではないことがお分かりいただけるだろう。
以上、三回に渡って、四つの論点から、現在の訪問介護の課題と再構築の方向性について述べてきた。「介護報酬が上がった、下がった」という話ではないことがわかるだろう。
もちろん、これをやれば、すべて課題が解決できるというわけではない。また、この制度矛盾やドタバタは訪問介護にかぎったことではない。それだけ、いまの介護保険制度には、その開始から四半世紀たった今も、「介護報酬が高い・低い」だけではない、根本的な制度課題が数多く横たわっているということだ。
これら、根本となる制度の土台を見直ししないまま、「地域包括ケアシステム」の名の元、自治体に責任を押し付け、介護崩壊を、指をくわえて見ているだけでは、厚労省の存在意義はない。同時に、ポピュリズムだけで、真の社会課題、介護課題に対峙できない政治家も同様だ。
【訪問介護の課題と再生 (全三回)】
訪問介護の課題と再生(Ⅰ) ~零細事業者の整理・統合~ 🔗
訪問介護の課題と再生(Ⅱ) ~集合住宅への訪問介護~ 🔗
訪問介護の課題と再生(Ⅲ) ~移動時間の報酬算定~ 🔗
<<< 介護のニュースを読む、ベクトルを掴む (TOPへ) >>>

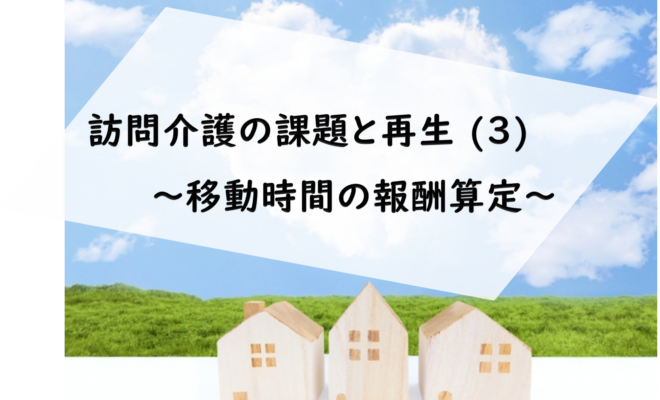

























この記事へのコメントはありません。