これからの後後期高齢者1000万人時代に求められるは、「自立要支援向け住宅」ではなく、「要介護向け住宅」だ。しかし、国はこれまで、その正反対の政策をとってきた。そして、その制度矛盾に付け込んだ、素人事業者が激増してきたのだ。
【矛盾だらけの高齢者住宅の制度】
一つは、要介護向け住宅の整備を、特別養護老人ホームで代替してきたことだ。
特養ホームは、老人福祉法に基づく、要介護高齢者の住まいの一つとなっている。
ただ、「介護対策」「住宅対策」だけではなく、建築費の高額補助や税制優遇、報酬加算などの「福祉対策」「低所得者対策」が複合的に行われているため、介護付有料老人ホームよりも、各段に低い費用で入所することができる。実際、ユニット型特養ホーム(月額費用15万円程度)と同程度の介護付有料老人ホームを整備すると、その価格は30万円になることがわかっている。その差額(年間180万円)は、社会保障費の負担となっている。
「ユニット型特養ホームに入れば、有料老人ホームの半額で入居できる」
「ユニット型特養ホームに入れない人は、その倍額を支払わなければならない」
つまり、ユニット型特養ホームは、ラッキー・アンラッキーの話でしかない。
更に、その一方で、それだけの高額な社会保障費を導入しながら、低所得者対策の不備によって、本来の対象である低資産低所得の「要福祉」高齢者が入所しにくい構造となっているなど、社会保障政策全体として見ると極めて非効率、不公平で、問題が大きくなっている。
二つ目は、「要介護向け住宅」に適した介護付有料老人ホームを規制し、重度要介護高齢者、認知症高齢者には対応できない、区分支給限度額方式の住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)ばかりを増やしてきたことだ。
寝たきりや認知症になると、「要介護高齢者に適した建物設備設計」「特定施設入居者生活介護の指定」が不可欠となる。しかし、この10年の間に、「区分支給限度額方式」を土台とした住宅型有料老人ホームやサ高住は、それぞれ3.2倍、8.8倍と激増しているのに対し、介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)の増加率は1.4倍に留まっている。
三つ目が、指導監査体制の崩壊だ。
高齢者住宅の対象は、身体機能・認知機能の低下した契約弱者であること、高齢者住宅は閉鎖的な環境になりやすいこと、自宅に戻れないため入居者や家族が弱い立場に立たされやすいことなどから、入居者保護を土台とする一定の強制力を持った指導・監査が必要となる。
しかし、厚労省の主管する「有料老人ホーム」と、国交省が独自に始めた「サービス付き高齢者向け住宅」という二つの制度の歪みで、指導監査体制は完全に崩壊している。その制度矛盾の中で、誰も管理しない違法な「無届施設」が激増し、わかっているだけでいまも全国で604件(2023年6月現在)が報告されている。「無届施設」といえば柔らかいが、これは必要な機能や届け出、情報開示を行っていない「違法施設」だ。数万人の高齢者が暮らしていると考えられているが、その実数さえも明確ではない。暴言・暴力などの身体虐待や本人の預貯金を私物化する経済虐待などの犯罪行為が横行しているが、厚労省はおざなりの調査を続けるだけで、この20年、完全に放置されたたままだ。
この三つの政策課題は、いずれも制度の根幹にかかわるものだ。いまや現在の高齢者施設・高齢者住宅に関わる制度の整合性は誰にも説明できない。政策に瑕疵があるというよりも、「やるべきことと正反対のことをやってきた」といっても過言ではない。
【ビジネスモデルの破綻・不正が蔓延する高齢者住宅】
この矛盾だらけの脆弱な制度の中で「介護は儲かる」「高齢者住宅は儲かる」と激増してきたのが「素人経営の高齢者住宅」だ。その問題点は、大きく分けて三つある。
一つは、「重度化対応の不備」。
高齢者住宅への入居を検討する高齢者・家族の基本となるニーズは「終の棲家」であり、介護が必要になっても生活できることだ。そのため、介護付、住宅型、サ高住を問わず、大半の高齢者住宅は「重度要介護・認知症になっても安心・快適」とセールスしている。
しかし、現在の介護付・住宅型有料老人ホーム、サ高住の中で「重度要介護・認知症高齢者」に適した生活環境の高齢者住宅は、その二割にも満たない。 「夜勤では40人の要介護高齢者を一人のスタッフが対応している」という報道があるが、それは、制度ではなくその高齢者住宅の労働環境の問題だ。
それは、要介護高齢者が安全に暮らせない生活環境は、介護スタッフが安全に介護できない労働環境でもある。介護できない建物設備、介護システムの高齢者住宅に重度要介護高齢者を無理やり入居させるために重大事故やトラブルが多発し、その過重労働や法的責任を一方的に押し付けられる介護現場からは「介護の仕事はブラック」と怨嗟の声が溢れている。
もう一つは、不正・違法行為の横行だ。
いま、住宅型有料老人ホームやサ高住で蔓延しているのが、「囲い込み」と呼ばれる不正だ。そのカラクリは、家賃や食費などを抑えて入居者を集め、系列の介護サービス・医療サービスを最大限に利用させることで、トータルで高い利益を上げるという「貧困ビジネス」だ。
「囲い込みは、違法ではなくグレーゾーン」と抗弁する識者もいるが、そこには、「不必要な介護・医療の押し売り」だけでなく、認定調査の改竄や介護報酬の不正請求など詐欺行為も多く含まれている。
適切な介護を受ける権利を奪われた高齢者が入浴中に放置され死亡するなどの痛ましい事故・事件も多発している。これらの制度矛盾や囲い込みの不正によって搾取される社会保障費は、最低でも年間2~3兆円規模に上る。国内の介護費の総額が11兆円規模であることを考えると、その金額の大きさがわかるだろう。これを自らの利権のために責任を曖昧にし、放置してきた厚労省、国交省の責任は極めて大きい。
「後後期高齢社会に高齢者住宅は不可欠」ということは述べた通りだが、制度の混乱と素人事業者の増加によって、あるべき姿とは全く違うものとなっている。グレーゾーン、不正行為で要介護高齢者、社会保障制度、介護人材をクイモノにする事業者が、巨額の利益を上げるという本末転倒のものになっているのだ。




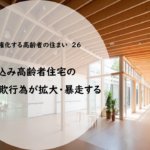



















この記事へのコメントはありません。