高齢者住宅は、特養ホームのような福祉事業ではなく、民間の営利事業・住宅事業だ。民間の知恵や工夫によって、低価格で高品質の商品・サービスを作ることが、後後期高齢社会を突破する活力になる。一律の基準を強制し、自由競争を過度に妨げることは望ましくない。
しかし、一般のマンションやアパートと同じかと言えばそうではない。
高齢者住宅産業が健全に発展し、入居者の生活を安定させるには、その土台となる法律・制度や、行政の役割・責任は大きい。
ポイントは三つある。
【長期安定的な制度設計】
高齢者住宅は不動産事業・住宅事業であり、かつ入居希望者は「終の棲家」を求めている。また、述べた通り、「後後期高齢者1000万人時代」は、2040年から2070年代まで長期にわたって続くことになる。そのため40年、50年という長期安定経営が不可欠だ。介護報酬を含め経営の土台となる制度が安定しなければ、事業経営だけでなく入居者の生活が不安定になる。
【公平・公正な事業環境・経営環境の整備】
営利事業は市場原理に基づくサービス競争が行われている。事業を発展させるか、倒産させるかは経営者の手腕にかかっている。ただ、高齢者住宅事業・介護サービス事業は、営利事業でありながら、その収入を公的な介護保険制度に依存するという類例のない極めて特殊な事業である。
そのため、法律や制度が、その事業性・収益性に及ぼす影響は、他の産業とは比較にならないほど大きい。公平公正な制度運用に基づくサービス競争が行われる土台が形成されなければ、優良な高齢者住宅の発展も、要介護高齢者の生活の安定もない。
【入居者保護の重要性】
高齢者住宅は老人福祉施設ではないが、一般の賃貸住宅でもない。
◇ 自宅に戻れない人が多く、入居者・家族が弱い立場に立たされやすい
◇ 高齢者は契約弱者であり、サービスの押し売りなど不利益な契約が行われやすい
◇ 要介護・認知症高齢者は、暴言・暴行などの虐待が行われても訴えられない
◇ 介護報酬の不正請求、契約違反が行われていても、入居者・家族にはわからない
◇ 入居者・介護スタッフが変わらないため閉鎖的で隠蔽体質になりやすい
その特性を考えると、入居者保護の重要性は、老人福祉施設の入所者とまったく同じだ。
営利事業であり、競争によって経営が不安定になりやすいこと、参入障壁が低いことなどを考え合わせると、契約内容の確認や入居後のリスクの説明を含め、福祉施設以上の強い情報開示、入居者保護施策が求められる。特に、要介護向け住宅の場合、倒産・事業閉鎖となれば、「居住する権利」が担保されていても、介護看護、食事などの生活支援サービスはすべてストップする。それは住み続けられないだけでなく、最悪の場合、命に関わる問題に発展する。そのため、運営後の定期的な指導監査だけでなく、事業計画は適切なものか、その地域ニーズに合致しているか、経営力・財政は安定しているか、契約内容に不適切なものはないかといった行政など第三者による開設前の事前チェックは不可欠である。
ここまで後後期高齢社会の高齢者住宅整備の論点について述べてきた。
これからの後後期高齢社会には、増加する重度要介護・認知症高齢者に対応できる「要介護向け住宅」の育成が不可欠なこと、その土台として長期安定的な制度設計、公平公正な競争環境の整備、入居者保護を基本とした法体系・制度体系が必要になることがわかるだろう。
しかし、残念ながら、実際はそれとは正反対の政策が取られてきた。
◇ 要介護向け住宅の代替施設として、全室個室の特養ホームを作り続けてきたこと。
◇ 要介護向け住宅の介護付有料老人ホームだけを規制して、重度要介護に対応できない区分支給限度額方式の住宅型有料老人ホームやサ高住ばかりを増やしてきたこと
◇ 厚労省と国交省に分かれて利権争いを繰り広げた結果、高齢者住宅には有料老人ホームとサ高住の二つの制度が存立し、その歪みで指導監査体制が崩壊していること。
「やってはいけないことだけをやってきた」と言っても過言ではない。厚労省も国交省も天下り先の確保や個人の出世欲など、目先の利権と補助金だけを目的に、長期安定的な制度設計とは正反対の政策を取り続けてきたのだ。
それが、現在の高齢者住宅業界が大混乱している原因だ。れは、劣悪なサービス、脆弱な経営で入居者の生活を不安定にするだけでなく、働く介護スタッフの労働環境の悪化、更には、違法行為による介護報酬の流出などあらゆる問題に発展している。その不正に搾取される医療介護費用は年間、数兆円規模に上る
次章からは、現在の高齢者の住まいの制度の課題について論ずる。

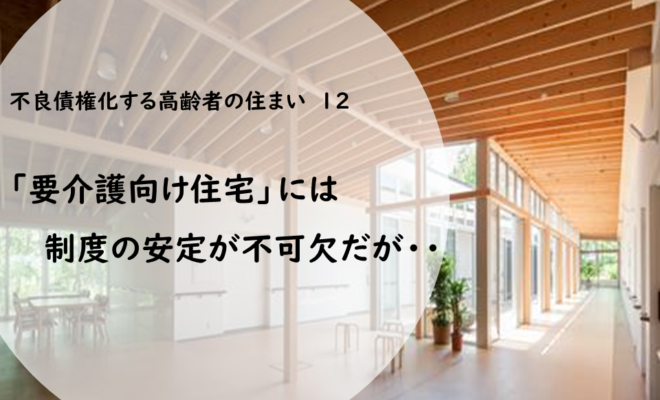
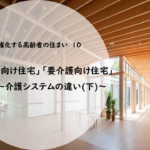
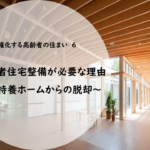
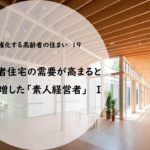


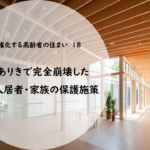
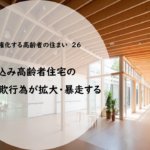
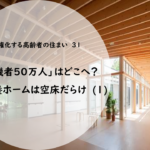

















この記事へのコメントはありません。