「介護報酬を上げて、介護労働環境を改善してほしい」
いま介護業界では、そういう声が高まっている。ただ、それは「家族の代わりに介護をしているから」「介護の仕事は排泄介助や入浴介助など大変だから」ではない。
高齢者介護は、要介護高齢者の身体機能の変化、認知症対応など、生活全般に関わる高度な専門知識・技能が必要とされる専門職種だ。同時に、小さなミスや一瞬のスキが重大事故、死亡事故につながる責任の重い仕事でもある。
高齢者介護は、決して、「家族介護の代替サービス」ではない。社会保障財政が極めて逼迫した状態であることは十分に理解しているが、自分が歳をとったとき、認知症になったときに「質の高いプロの介護」を受けたいのであれば、その専門性をもう少し高く評価してほしいと訴えているにすぎない。
介護の仕事がブラックなのではない
しかし、それをわかっていないのが、不正事業者や介護労働環境の悪化を放置してきた厚生労働省と、みずからの経営責任を全く果たそうともせず、「介護は儲かりそうだ」と安易に参入し、介護現場に負担を押し付けている素人の介護経営者だ。
各地域の認知症介護、老人福祉対策の要である特別養護老人ホームの管理者は、高齢者介護、老人福祉に対する深い知識、経験、重い責任が求められる。その責務を担うには介護福祉士、社会福祉士、ケアマネジャーなどの有資格者であり、かつ介護現場での実務経験が不可欠である。
しかし、実際は、無資格未経験の行政からの天下り公務員や地方議員の親族が多いことが知られている。そのための体裁だけの施設長任用資格は、厚労省が主管する公益法人の「短期通信教育」で取得できる。それさえ本人ではなく現場の介護スタッフが代筆させられているというのが現実だ。知識も経験も、やる気もない天下り公務員や地方議員やその親族のために支払われる「理事報酬・施設長給与」だけで、年間数百億円を超える。
以前(15年ほど前)、とある政党の厚生労働大臣が、国会で「介護人材不足への対策」を聞かれ、「ハローワークの求職者に介護の仕事を積極的に進めるように指示した」と言っていた。それを聞いて絶句した。
政治家を含め厚労省が、いかに高齢者介護の専門性を軽視しているか、わかるだろう。国や政治家は財政悪化を口にするが、「介護は厚労省や自治体利権」「介護は仕事がない人の仕事」程度にしか思っていないということだ。
残念ながら、これは介護経営者も同じ。
人材不足を「介護報酬の低さが原因」と責任転嫁する介護経営者は多いが、そもそも、その低い待遇・給与で、安全に介護できない危険な労働環境の高齢者住宅を造ってきたのは誰だろう。巨額の利益を上げ、次々と上場を果たしながら、介護事故の多発を放置し、それをすべて介護現場の責任に転嫁し、その労働環境の改善を見直そうとしないのは誰だろう。
介護報酬がその専門性と比較して低いことはその通りだが、「介護現場の労働環境改善のために、あなたはどんな経営努力をしているのか」と聞くと、ゴニョゴニョとほとんど何もしていない経営者・理事長がほとんどだ。数年前、ある介護経営者が自嘲気味に、「この業界は、労働環境の改善、経営努力を何もしなくても、人が集まらないのは、利益がでないのは介護報酬の責任だと口を開けて待っていれば良い」「介護経営どころか、介護そのものを知らない人がほとんど」と笑っていたがその通りだ。
いま、そのツケが介護現場を苦しめ、その毒が業界全体にまわってきているのだ。
介護という仕事がブラックなのではない。
「社会保障費の悪化」を旗頭に、その専門性を軽視し、介護労働環境や待遇改善を放置してきた厚労省と、介護の現場を知らない「利益ありき」の素人事業者の大量参入によって、「介護の仕事なんてやっていられない」と介護業界からどんどん人が逃げ出しているのだ。
高齢者住宅バブルの崩壊は目の前に迫っている
いま、右肩上がりで増えてきた高齢者住宅業界も曲がり角を迎えようとしている。
介護スタッフ不足や制度変更リスク、入居一時金の長期入居リスクの顕在化によって、「こんなはずではなかった」「このままでは数年後に経営が破綻する」と、事業を手放す経営者が増えているのだ。
それは個人、中小事業者だけでなく、これまで高齢者住宅業界をけん引してきたトップ10の大手事業者も次々と事業譲渡され経営主体が変わっている。短期利益を目的とした、投資・投機目的の投資ファンドも参入し、二度、三度と経営者がかわる高齢者住宅もある。自社株買いで、短期利益を独占するかのような動きも始まっている。
この現象によく似ているのが、平成初期に起きたリゾートバブルの崩壊だ。当時、わたしは都市銀行の銀行員だった。全国で無茶苦茶なリゾート計画が発表され、ゴルフ会員権は投機対象の金融商品となり数千万円、数億円にまで高騰した。バブルが崩壊するとその価値は下降の一途を辿り、最後は誰がその債務(ジョーカー)を背負うかという「ババ抜き」の状態に陥った。いままさに高齢者住宅業界では、同じことが起きようとしているのだ。
個人経営のサ高住の倒産は少しずつ増えてきている。「高齢者住宅M&A」の相談会には、デベロッパーやコンサルタントに騙された個人経営者が大挙押し寄せているという。あと数年のうちに、その波は大手事業者を飲み込むことになる。
もう一度言おう。高齢者住宅が倒産する理由は、数が増えすぎたからでも、介護報酬が低いからでもない。根幹となる制度設計、商品性、ビジネスモデルがあまりにも脆弱だからだ。すでに、高齢者住宅バブルは崩壊前夜に入っている。あと三年か、五年か……、その時は確実にやってくる。
「私たちが直面する後後期高齢社会とはどのような社会なのか」
「なぜ、高齢者の住まいを取りまく制度は欠陥だらけなのか」
「長期安定経営が難しい高齢者住宅にはどのようなタイプのものがあるのか」
「なぜ、『介護の仕事はブラックだ』と考える介護スタッフが増えているのか」
「他の業界にない高齢者住宅M&Aの危険な兆候とは何か」
「最後にバブル崩壊のジョーカーを掴むのは誰なのか」
「厚労省が旗を振る地域包括ケアシステムの真の目的はどこにあるのか」
「低価格の要介護向け住宅をどのように整備・統合していくのか」
高齢者住宅業界が抱える課題と大規模倒産時代、その後の未来について考える。


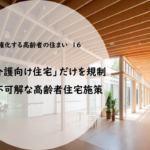
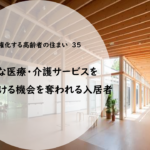

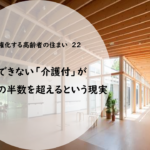



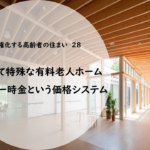

















この記事へのコメントはありません。