ご存知の通り、現在の高齢者住宅の制度は、厚労省の主管する「有料老人ホーム」と国交省の主管する「サービス付き高齢者向け住宅」に分かれている。その制度上の違い、設置基準の違いについては、説明することは可能だが、そもそも「どうして、高齢者住宅に二つの基準が必要なのか」は、誰にも説明することはできない。その理由は、「各省庁の利権があるから」以外になにもない。
前回述べたように、この有料老人ホームと、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)から始まる高齢者住宅利権の争いは、その制度矛盾の隙間で、無届施設、類似施設という違法な高齢者住宅を生み出してきた。
問題は、それだけではない。
サービス付き高齢者向け住宅は、当初の目的を無視した制度
厚労省と国交省は、高専賃として新しい登録基準を満たしたものは、食事や介護看護などの生活支援サービスを提供するものでも、有料老人ホームとしての届け出を不要とした。
つまり、同じ民間の高齢者住宅でも、「有料老人ホーム」は事業計画・収支計画・建物設備計画などを作成し、管理運営、サービス内容・契約内容、費用について行政の事前チェックを受けなければならないが、「高専賃」は事業計画も契約内容のチェックもないまま、紙一枚登録用紙に記入するだけで、開設することが可能になったのだ。登録基準を満たしたものというのが前提だが、その登録内容が正しいかどうか誰もチェックしないし、間違っていても指導も罰則もない。
さらにその矛盾を拡大させたのが、高専賃の後継制度であるサービス付き高齢者向け住宅だ。
もう一度、思い出して考えていただこう。サ高住のはじまりは、一般の賃貸住宅を登録させ「元気な高齢者の住まい探しを支援する高円賃・高専賃の制度」(2001年)だ。賃貸マンション選びは、事前に仲介業者から建物設備の内容について説明を受け、内見を行う。説明内容が間違っていれば訴えることもできるし、気に入らなければ解約すればよい。「高齢者を断らない」というだけの一般の賃貸マンションであれば、登録内容の確認・チェック程度で、特別な指導や監査は必要ないかもしれない。
しかし、現在のサ高住は、共用部に食堂や特殊浴槽などが配置され、直接的・間接的に食事や生活相談、介護看護サービスが提供されている。いまやその八割、九割は、はじめから「重度要介護高齢者、認知症高齢者を対象」としている。中には、対象は要介護高齢者のみ、自立要支援高齢者は対象外としているところも多い。補助金や優遇施策によって、その数だけは爆発的に増えたが、いつの間にか、「普通の賃貸アパート・マンションを探したい元気な高齢者の住まい探しの支援」という当初の目的・役割は跡形もなく消えているのだ。
それでもまだ、補助金を出して作り続けているのだ。
サ高住は厚労省と国交省の利権と補助金争いの中で生まれた意味不明の制度だという理由がわかるだろう。その批判が高まると、いままた「サ高住の一部は有料老人ホームに該当する」とさらに意味不明なことを言い始めている。恐らく、本人たちもすでに自分が何を言っているのか、わからないのではないだろうか。
官庁の利権目的だけに利用された高齢者住宅
確かなことは、この二つの制度の混乱によって、無届施設だけでなく、有料老人ホーム、サ高住含め高齢者住宅の入居者保護施策が完全に崩壊しているということだ。
前章で高齢者住宅の制度設計に必要不可欠な視点として、三つのポイントを挙げた。
【長期安定的な制度設計】
高齢者住宅は不動産事業・住宅事業であり、かつ入居希望者は「終の棲家」を求めている。
そのため30年、40年という長期安定経営が不可欠だ。介護報酬を含め経営の土台となる制度が安定しなければ、事業経営だけでなく入居者の生活が不安定になる。
【公平・公正な事業環境・経営環境の整備】
営利事業は市場原理に基づくサービス競争が行われている。事業を発展させるか、倒産させるかは経営者の手腕にかかっている。ただ、高齢者住宅事業・介護サービス事業は、営利事業でありながら、その収入を公的な介護保険制度に依存するという類例のない極めて特殊な事業である。
そのため、法律や制度が、その事業性・収益性に及ぼす影響は、他の産業とは比較にならないほど大きい。公平公正な制度運用に基づくサービス競争が行われなければ、優良な高齢者住宅の発展も、要介護高齢者の生活の安定もない。
【入居者保護の重要性】
◇ 自宅に戻れない人が多く、入居者・家族が弱い立場に立たされやすい
◇ 高齢者は契約弱者であり、サービスの押し売りなど不利益な契約が行われやすい
◇ 要介護・認知症高齢者は、暴言・暴行などの虐待が行われても訴えられない
◇ 介護報酬の不正請求、契約違反が行われていても、入居者・家族にはわからない
◇ 入居者・介護スタッフが変わらないため閉鎖的で隠蔽体質になりやすい
しかし、実際は、その正反対の政策が取られてきたということがわかるだろう。
「老人福祉施設」と「高齢者住宅」の役割の混乱。
「特定施設入居者生活介護」と「区分支給限度額方式」の混乱。
「有料老人ホーム」と「サービス付き高齢者向け住宅」の混乱。
いまや、なぜこんなことになってしまったのかさえ、誰にも説明できない。
もう、だれも説明する気さえないと言った方が良いだろう。
サ高住のトラブルが多発すると、国交省は慌てて、形式上だけ立ち入り調査などの指針を取りまとめたが、付け焼刃のようなもので、誰が監査するのか、どのように行うのか、その判断は誰がするのかなど何も決まっていない。「一応、対策やってます」のポーズ以外の何物でもない。
その一方で、「サ高住は建物だけなので介護サービスは無関係」と知らぬ存ぜぬを決め込み、厚労省は「サ高住はしらない」「介護保険の指導監査は自治体の責任」とそのボールを投げ捨て、自治体は「福祉施設ではないので選択した高齢者・家族の責任」と、それぞれ言い訳と責任の押し付け合いに終始している。全国で、有料老人ホームやサ高住などの事故やトラブル、介護虐待、介護放棄などの異常事態が多発しているが、それらは氷山の一角でさえない。国は利権と補助金目的に制度を作っただけで、「あとは知らない…」「責任なんてしらない…」と無視を決め込んでいる。♬そんなの関係ねぇ、そんなの関係ねぇ♬という、あまり愉快ではないお笑いが流行ったことがあるが、それを地で行くのが厚労省と国交省が推進した高齢者住宅施策だ。
介護保険制度の発足後、将来性の高いビジネス・事業として「高齢者住宅に参入したい」という相談は多かった。しかし、多くの経営者が口にしたのが「こんな不安定な制度ではとても参入できない」「国が何をしたいのか訳がわからない」「まともなビジネス環境だとはとても言えない」という言葉だった。
残念ながら、その通りだ。
その一方で、制度上の課題や高齢者住宅の特性を理解することなく、「高齢者住宅の需要が増える」「高齢者住宅はまだまだ不足している」という過剰な期待だけで、素人事業者が大量に参入してきた。また、そこに形ばかりの業界団体や規制団体、国交省、厚労省からごっそりと天下りが行われている。
高齢者住宅産業の育成の名のもと、一部の政治家や官僚が利権目的に暗躍し、「矛盾だらけの制度」「素人事業者」によって作られた欠陥商品・違法商品が蔓延しているのが、現在の高齢者住宅業界なのだ。

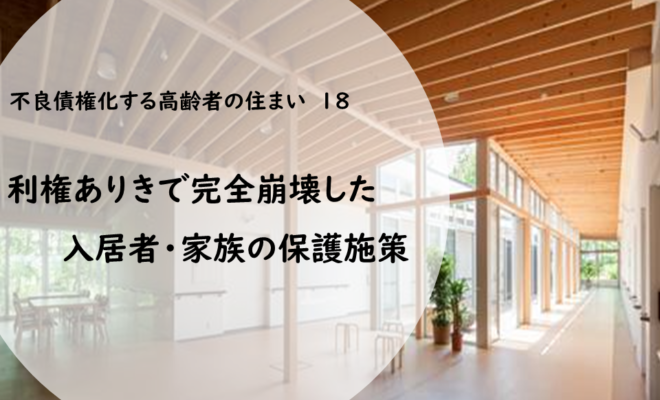





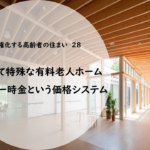
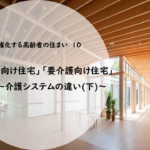

















この記事へのコメントはありません。