ここでは、介護休業制度の実際の取得例について、解説していきます。
今回は、「介護休業取得のポイントⅢ 🔗」 で述べた、骨折や脳梗塞などで突然入院し、自宅に戻ることを検討したけれど、一人暮らしが困難で老人ホームを選んだ例です。
介 護 問 題 の 発 生
私は四〇代、京都の小さな出版社(タウン誌担当)で、編集の仕事をしています。
一度結婚しましたが、離婚し、子供はいません。母は10年前に亡くなっており、父は八五歳で実家のある大阪で一人暮らし、愛知と広島に2人の兄(7歳上、5歳上)がいます。
五月のある金曜日、仕事が終わり帰る準備をしていたところ、「父さんが倒れたらしい。すぐに病院に行ってほしい」との長兄からの電話。とるものもとりあえず駆けつけたところ、ちょうど手術が終わったところでした。庭の手入れ中に倒れたところを運よく近所の人に発見されたということで、手術は成功したのですが、年齢のこともあり、リハビリを行っても左半身の麻痺が残り、車いす生活になるかもしれないとのことでした。
翌日、駆けつけた兄たちと三人でこれからのことを話し合うことになりました。
どちらも、「転勤族だし子供もいるので、引き取って介護をすることは難しい」というのが結論でした。そう言うであろうことはわかっていましたし、直接言葉にしないものの「実家から職場に通うことは難しいか…」と、私が家に戻って父の面倒を見てほしいと考えているようでした。父には3000万円ほどの預貯金があり、年金も月額18万円程度はあるので、私が仕事を辞めてもすぐに生活に困ることはありません。介護費用としてそれぞれ月5万円程度(合計10万円)であれば負担できることや、自宅や父の預貯金についても私が自由に使ってもよいと言いました。
ただ、私にも事情はあります。小さな出版社の一編集員ですが、今のタウン誌の編集という仕事が好きですし、社長や一緒に働くスタッフにも恵まれています。いまの仕事を辞めてしまうと、同じような条件の仕事を見つけることはできません。実家から職場までは、片道2時間程度の距離ですが、仕事の性格上、締め切りが近くなると夜遅くまでの残業も増えるため通うことは不可能です。
また、私が離婚するときに、感情の行き違いがあり、父との関係はあまり良くありませんでした。兄たちは子供もいることから、お正月や夏休み、春休みなど、年に数回は、子供達を連れて泊りがけで遊びに来ていたようですが、私は二ヶ月に一度程度、様子をみがてら買い物や片付けに出向くくらいで、話が弾むこともなく、二時間程度ですぐに帰ってくるという関係でした。
それでも私が仕事を辞めるのが一番良いのだろう(それしかないだろう)ということはわかっていました。母が10年前にガンになったときに「お父さんのことお願いね…」と手を握られたことも頭の中から離れません。社長や編集長には何と伝えればよいだろう、何といわれるだろう…契約社員にしてもらう、パートにしてもらうことはできるだろうか…、とあれこれ考えながら帰りの阪急電車に乗っていると、窓の外が歪んで見えました。
上 司 に 相 談
どのように話をすればよいか何度も独り言を繰り返し、ほとんど眠れなかったので、ポイントだけをメモにしておきました。
◆ 一人暮らしの父が脳梗塞で半身麻痺となり、日常生活に介護が必要になる
◆ 二人の兄がいるが遠方に住んでいることや、子供もいることなどから介護は難しい
◆ 私も今の賃貸マンションで同居することは難しく、実家に帰って介護をする必要がある
◆ 入院期間はリハビリを含め二ヶ月程度を予定(リハビリ病院への転院を含む)
◆ その後、父の介護のために仕事を辞め、実家に戻ることを考えている
月曜日に、出勤してすぐに上司である編集長と社長に話をしました。冷静に話をしたつもりでしたが、最後のところで自分でも、感情がこみあげてくるのがわかりました。急なことで驚かれたようでしたが、社長は自分の母親を自宅で介護された経験をお話しいただいて、
「介護は本人だけでなく、家族の生活・人生にも関わってくる大きな問題」
「突然のことで気持ちも混乱している中で、重大な選択をバタバタと決めると良くない」
「今はテレワークや介護サービスもあるので、一番良い方法をみんなで考えよう」
と仰ってくださいました。その優しい言葉にぽろぽろと涙がでました。また、編集長は、知り合いが地域包括支援センターで相談員の仕事をされているとのことで、「色々相談してみれば…」とわざわざ電話をしてくださいました。
翌日、編集長から紹介いただいた智子さんにお話しを聞いていただくことができました。
母はガンで入院しそのまま亡くなったので、介護保険のことは「トイレの介助」「入浴の介助」が必要になる、「デイサービス」「訪問介護」などのサービス、「要支援」「要介護三」といった漠然とした知識しかありませんでした。また、その時までは「仕事を辞めなければいけないのか」「会社にどのように伝えようか」ということばかりが頭の中で回り続け、実際に必要な手続きや退院後の生活については考えていませんでした。
智子さんと話をする中で、大切なアドバイスをたくさんいただき、落ち着いて考えることができました。
① 今すべきことは、リハビリと心のケア
突然、脳梗塞になって一番精神的に落ち込んでいるのは父であるということ(そんなことさえ忘れていました)。精神的ショックや脳梗塞の影響から認知症になる人も多いことから、意欲をもってリハビリができるように、家族は精神的なサポート・ケアを積極的に行うこと。「頑張って」「しっかり」といった言葉は本人を追い詰めることもあるので、「一緒に頑張ろう」といった寄り添う声掛けや、落ち着くように手や身体をさするといったケアも必要。
② 介護保険の申請は落ち着いてから
「介護が必要になる➾介護保険の申請が必要」と考えてしまうが、脳梗塞や脳出血などで状態が安定していない時には介護保険申請はできない。今はまだ脳梗塞の治療やリハビリが優先で、要介護認定調査の申し込みは、その治療経過によって状態が安定し、リハビリによって介護の必要度やその方向性が見えてきてから。
③ 先のことを見据えながらも、先のことを考えすぎない
リハビリや残存機能によって、どのような介護が必要になるか、自宅で生活し続けられるか否かは一人一人違う。介護の問題から目をそらせてはいけないが、逆にあれこれと先のことまで考えすぎて不安ばかりが増大するのも良くない。「今できることをしっかりやること」「方向性が見えてくれば考える」という割り切りが必要。
「仕事を辞めなければならないかもしれない」「みんなに迷惑をかけないよう早めの決断が必要」ということが心の負担になっていたのですが、私だけでなく「親の介護で仕事を辞める人は多い」と話されたうえで、「親の介護をしたいので仕事を辞める」というのと、「親の介護で仕方なく仕事を辞める」というのは全く違うことだよと言われました。
少しでも「仕方なく…」という気持ちがあるのなら、絶対に後悔するよとも言われました。「あなたがどうしたいのかが一番大切」「仕事か介護かという二者選択ではなく、仕事を続けながら介護できる体制を一緒に考えましょう」と言ってくださいました。
介護休業制度の取得事例 Ⅱ ~脳梗塞から老人ホーム~ (下) へ続く<<<
>>>>新連載 介護離職をしない、させない社会へ (TOP)

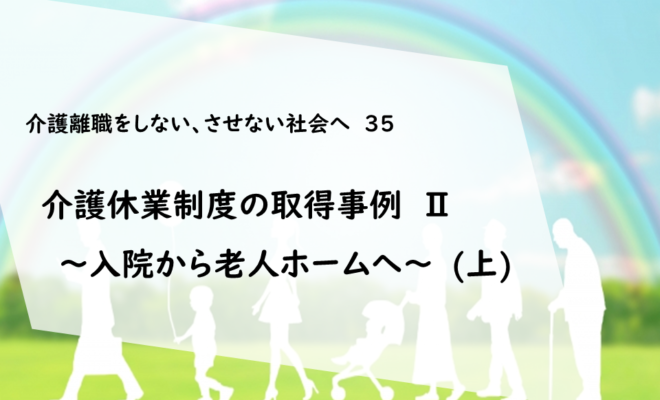

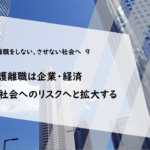

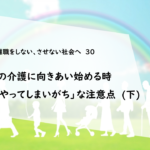

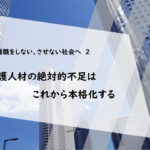
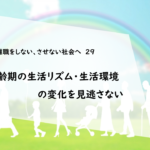








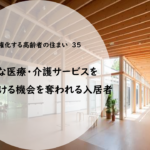









この記事へのコメントはありません。