介護休業制度の取得事例Ⅰ ~骨折・入院から自宅復帰~(上) 🔗 >>>から続く
ここでは、介護休業制度の実際の取得例について、解説しています。
前回に引き続いて、骨折や脳梗塞などで突然入院し、その後のリハビリで、自宅に戻ることのできた事例について解説します。ポイントになるのは、介護休業の取得方法です。
母は自宅に戻って生活、介護休業の取得
母は最初の病院で手術を行い、二週間後にリハビリテーション病院に転院した。
本人も「なんとか家に帰りたい」とリハビリを続けた結果、若干歩行が不安定で杖が必要となるものの、自力で歩行やトイレに行くことができるようになった。
リハビリ病院の入院中に要介護認定申請を行い「要介護2」。担当のケアマネジャーさんも決まり、入浴と筋力維持のリハビリを兼ねて週に二回の通所リハビリの利用を提案された。買い物も心配したが、母はこれまでからスーパーの宅配サービスを利用していたことや、足りないものは私たちが帰省した時に買いに行くということになった。
また、我が家のトイレは古く狭いので、ルートへの手すり、入口の段差解消などを含め、住宅改修を行うことにした。この住宅改修については、母の一時外出に付き添って、ケアマネジャーさん、リハビリ病院の先生(作業療法士さん)も実家に来ていただき、大工さんも一緒になって必要な改修について検討してくれた(改修費用の一部は介護保険から戻ってくる)。
こうして着々と自宅に戻る準備が進む一方で、「本当に大丈夫だろうか…」という漠然とした不安は消えなかった。日々の料理や通所リハビリの準備、宅配サービスへの対応はできるのか、また自宅で転倒したりしないか、家に閉じこもりがちにならないか…等々。母も、私たちにできるだけ迷惑にならないように、「一人でも大丈夫」というものの、転倒、骨折したことで自信を失っており、これまで通りの生活ができるかどうか不安を感じている様子だった。
その話を、退院後の在宅復帰の準備状況の報告に合わせて、出雲さんに相談すると「介護休業を検討してみては…」と勧められた。
介護休暇・介護休業については、最初に説明を受けたが、今回は、私が直接、排泄介助や入浴介助をする必要もなく、どちらかと言えば「介護休業を取らなくていいように」「会社にできるだけ迷惑かけないように」と土日を使って(有給も二日使った)、対応をしてきたことや、オムツ交換や入浴介助をするわけではなく、「今さらですか?」という感じはあった。
ただ、出雲さんの話を整理すると、
◇ 家族も本人も、自宅での生活に向けて不安を感じるのは当然のこと。
◇ 万全の準備をしたつもりでも、予想しない問題があれこれたくさん出てくる。
◇ 身体機能低下の一方、「慣れた家だから」と過信するため、退院直後の事故は多い。
◇ 家に戻ってすぐに再び骨折すると、次は自宅で生活できなくなるリスクが高い。
ということだった。
電話を切った後に送られてきたメールには、「お仕事やお立場もあると思いますが、一度課内のみなさんや上司の方とご相談ください」というメッセージと共に、「介護休業申請書」「介護休業取得の流れ」「介護休業に向けての業務調整予定表」という三つの書類が添付されていた。
再び、製造部長に相談すると驚いたようだったが、「まぁ、勤続25年では二週間のリフレッシュ休暇をとるんだし(社内制度)、連絡もつくんだから、大丈夫じゃないか…」と課内での調整を進めるよう指示を受け、部としてもバックアップしてくれることになった。
介護休業の取得とその後
それほど繁忙期ではなかったことや、課内のスタッフの協力、予定されていた外部業者との打ち合わせも前倒しすることで、母の退院の五日前から約一ヶ月(五週間)の予定で介護休業をとることができた。
介護休業を退院の五日前から取ったのは、自宅の住宅改修に立ち会うためだ。
合わせて、退院後の介護サービスについて、現在入院中のリハビリ病院のソーシャルワーカー、医師、作業療法士、在宅で母の介護をお願いするケアマネジャー、通所リハビリ(週2回)の介護スタッフ、訪問介護(週2回)のヘルパー、住宅改修の大工さん、介護ベッドの福祉用具の方など、お世話になる皆さんとのケアカンファレンスに出席することができた。
これだけたくさんの人が、母がどうすれば安全・快適に生活できるか、転倒を繰り返さないため何が必要か、何に注意してサービスを利用するか、また母にもどんな点に注意をして生活してもらうか…等々について真剣に議論していただいているのを聞いて、家族が漠然と考えていた介護と、専門的・科学的に提供されるプロの介護とは、ここまで違うものかと驚いた。
これまでも、「介護の仕事は大変だ」「家族の代わりに介護をしてもらってありがたい」とは思っていたが、もし私が自宅に戻って、家族で介護をしていても、とてもここまでのことはできない。
また、実際に自宅にもどって生活を始めてみると、宅配サービスの置き場所や連絡、郵便ボックスの位置、灯油ヒーターの給油、電子レンジの買い替え(以前から調子が悪かったらしい)など、些細なことではあるが、これまで当たり前にできていたことが難しい…ということがたくさん見つかった。それをどうするのか一緒に考えたり、場所を移したり、買い物に行ったりすることができた。また、火災のリスクを考えて、ガスコンロからIHコンロに、電話も特殊詐欺防止ができる録音付きのものに変えた。
母にとっては、私が一ヶ月の休みを取って家に帰ってきたことは「安心」というだけでなく、「嬉しい」という気持ちが大きいようで、精神的にも余裕ができ、元気になった。私の前では言わないけれど、友人・知人から退院祝いの電話がかかってきたとき、「息子が一ヶ月も休みを取って帰ってきてくれた」と何度も言っていた。「母が昔の写真を出して来て、葬儀の時の見栄えのいい写真を今から選んでおく」「生命保険とか大切な書類はあのタンスの一番下に入っている」と笑い、と、私が知らなかった生まれたときの話や小さいころの話も聞くことができた。
私も、介護休業を取らなければ、「一人で大丈夫だろうか」「退院後の生活に適応できるか…」と仕事中も考えることになっただろうし、何度も有給休暇をとる必要があっただろう。母が無理をして転倒したり、閉じこもりがちになったり、うつ病や認知症になっていたかもしれないとも思う。
休業中は会社のことも気になったが、会社側からは連絡がなく、一度こちらから「変わりないか」と電話しただけだった。結局、一ヶ月の予定でとった介護休業だったが、母が「もう大丈夫だから早く仕事に戻れ…」というので、実際は三週間程度に縮まった。今は、私が実家でネットを見たり、仕事の連絡に対応できるようにとひいたWEB会議システムを使って、母も遠方の姉や孫たちとも話をしている。
今回の親の介護問題では、製造部長や課内のみんなだけでなく、人事部の出雲さんには大変お世話になった。母や姉からは、積極的に介護休業の取得や一人一人の社員のことを考えてくれている良い会社だ…と言われ、その通りだと思い、あらためて感謝している。
また、同年代での集まりでは、「介護休業どうだった?」と聞かれることが増え、現在介護をしているか否かに関わらず、みんなそれなりに気になっているのだろうと思う。
母が一人暮らしに戻ったことで、またどこかで転倒したり、病気になってどこかで介護が必要になるかもしれないが、介護保険のことやいざというときにどうすればよいのか、どんな方法があるのかもよくわかった。社内で困っている人がいれば、積極的に自分の経験を伝えることができればと思っている。
>>>>新連載 介護離職をしない、させない社会へ (TOP)

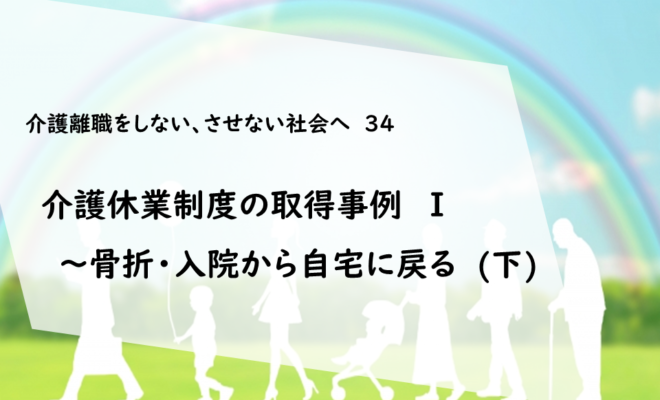




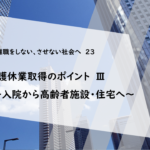
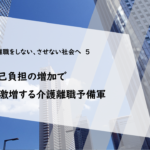


















この記事へのコメントはありません。