マスコミ報道を含め、いまでも「介護」と「福祉」という言葉を混同して使っている人が少なくありません。それは介護保険制度がスタートする2000年まで、高齢者介護は老人福祉法の中で行われてきたからです。
しかし、現行制度において、介護保険法は要介護高齢者に介護サービスを提供するための社会保険の法律であり、介護虐待やネグレクトなど要福祉高齢者を対象とした老人福祉法とは、根本的に役割が違います。「医療=福祉」ではないのと同様に、「介護=福祉」ではありません。
ただ、これは言葉上の混乱だけではありません。この介護保険と老人福祉の二つの制度に横たわる矛盾の修正も、介護保険・老人福祉を含めた、社会保障制度全体の立て直しには不可欠なものです。
社会福祉法人と民間介護サービスが抱える矛盾
社会福祉法人が行うことのできる社会福祉事業は、「第一種社会福祉事業」と「第二種社会福祉事業」に分かれています。老人福祉に関わる第一種社会福祉事業は、「特別養護老人ホーム」「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」などの入所系施設。第二種社会福祉事業は、「老人居宅介護等事業(訪問介護)」「老人デイサービス事業(通所介護)」「老人短期入所事業(ショートステイ)」「小規模多機能居宅介護事業」などです。
このうち、第一種社会福祉事業は、社会福祉法人(または市町村)しか運営できません。そのため、前回述べたように、福祉ケースや困難ケースへの対応が、より強く求められるようになるでしょう。一方で、第二種社会福祉事業の訪問介護や通所介護は、営利目的の介護サービス事業として株式会社などの一般企業も行うことができます。ただ、ここでいま発生しているのが、社会福祉法人と株式会社が運営する第二種社会福祉事業の運営格差です。
デイサービス(通所介護)を例に挙げると、社会福祉法人は営利法人ではないため、事業税や法人税、固定資産税等は非課税、もしくは減免されています。特養ホームに併設されている場合、建設補助も拠出されており、土地建物や車両は無料貸与、厨房も特養ホームと共有ですから、調理費などの運営コストも抑えることができます。
ただ、通所介護事業として介護保険から受け取る報酬単価は、社会福祉法人も株式会社も同じであるため、同じ30名定員規模、同程度の人員配置のデイサービスで比較すると、その収支差額は年間一千万円規模になります。加えて、高い利益があっても社会福祉法人は非課税なので、税収アップにもつながりません。
これは利益率の差だけではありません。
いま、特養ホームよりも不足していると言われているのがショートステイ(老人短期入所事業)です。ショートステイは、要介護高齢者本人のためというよりも、自宅で親や配偶者を介護している家族のレスパイト(休息・負担軽減)のために不可欠なサービスです。しかし、「体調が悪いので一週間だけ施設で介護してほしい」「急な法事でその間だけ利用したい」と思っても、多くの地域で、予約だけで一杯、すぐには利用できないというのが現実です。
ただ、このショートステイは第二種社会福祉事業です。株式会社が参入することができますが、民間経営で稼働しているところはほとんどありません。介護付有料老人ホームの空床をショートステイとして活用するという政策も出されましたが、「お試し入居、体験入居」が中心で、ショートステイとしてはほとんど稼働していません。その理由は、社会福祉法人の運営するショートステイとの運営格差があまりにも大きく、事業として成り立たないからです。
現在のショートステイの大半は、特養ホームに併設されています。言い換えれば、「高額の建設補助」「事業税・法人税は非課税」「高い介護報酬」「手厚い介護看護体制」「別途厨房や送迎用の車両費は不要」など二重三重に優遇されているということです。これを民間の介護サービス事業として行おうとすると、同等のサービス・人員配置でも、特養ホーム併設のショートステイの二倍以上の価格設定になるため、需要が高くてもこの運営格差が壁になって増えないのです。
社会福祉法人と民間介護サービスの役割の明確化
これは、「社会福祉法人は優遇されていてケシカラン」「運営格差があるのは不公平だ」という単純な話ではありません。これら2000年までの老人福祉時代の旧弊が、社会保障費の増大、介護サービス整備の障壁になっているということです。そのため、社会福祉法人と民間介護サービスの役割の明確化と共に、その社会保障費の増加や障壁となっている運営格差は見直されることになります。
① 第二種社会福祉事業の運営格差の見直し
一つは、第二種社会福祉事業に対する補助・優遇施策の見直しです。
第二種社会福祉事業である訪問介護やデイサービスについては、社会福祉法人に対する補助金支出や車両の無償貸与などの見直しが行われることになります。社会福祉法人に対して一律に行われている税制優遇についても、「第二種社会福祉事業に対しては対象外」となる可能性は高いと考えています。
② 社会福祉法人に対する第二種社会福祉事業の役割の明確化
二つ目は、社会福祉法人が行う第二種社会福祉事業の役割の明確化です。
いま、介護サービス事業者で介護スタッフに大きなストレスになっているのが、家族や利用者から暴力・暴言・セクハラを含めカスハラです。介護人材離れの大きな原因ともなっており、それを理由に、サービス利用を断る民間事業者は増えています。これからは、介護需要の増加に供給が追い付かない地域が多くなるため、明確な宣言はしないとしても、民間企業では「困難ケース・トラブルの認知症高齢者はお断り」というところが増えてくるでしょう。
しかし、そうなると、周辺症状のある独居認知症高齢者の多くはサービスの利用ができなくなる可能性があります。そのため、認知症・家族トラブルなどで民間介護サービス事業者が断る福祉ケース・困難ケースへの受け入れも、一定、社会福祉法人が義務付けられることになります。
③ 採算性の低い地域での介護サービスの実施
今後、特に地方部、山間部などで課題となるのが、小規模の集落、都市部から離れた僻地で暮らす高齢者に対する在宅サービスをどのように行うのかという問題です。これら採算性の低い地域には、民間の介護サービス事業者は参入しないため、社会福祉法人に一定の役割が求められることになります。
この三つの対策については、一定の指針が厚生労働省から示され、その実務については、「地域包括ケアシステム」の中で、それぞれの市町村に委ねられることになるでしょう。
例えば、①の第二種社会福祉事業に対する補助や税制優遇に対する見直しも、②の困難ケースへの対応、③の採算性の低い地域へのサービス実施などを、積極的に行う事業者に対しては、「市町村独自での補助」「当該対象となる事業所・サービス・法人には税制優遇を続ける」といった「アメとムチ」が使い分けられることになります。
逆に、これらの対策ができない事業者は、社会福祉法人として不適格として「補助金の返還」を含めた罰則を受ける可能性もあります。いずれにしても、「福祉機能強化」「透明性の確保」「自治体との実務的な連携」は、これからすべての社会福祉法人の事業経営、事業継続の根幹となることは間違いないでしょう。
これは、「税制優遇がなくなる」「補助金が削られる」といった、表面的な収支の些末な問題ではありません。困難ケース・福祉ケースは、一般的な介護サービスとは比較にならないほど、高い知識・技術が求められ、介護現場に重いストレスもかかります。トラブル対応や責任の明確化など行政との連携も含め、組織として対応できない社会福祉法人は、離職者が激増し事業継続が困難となります。
福祉機能の強化は、理念ではなく、経営課題です。
続く <<<社会福祉法人は冬の時代を迎える (Ⅲ) ~特別養護老人ホームの未来~
<<< 介護のニュースを読む、ベクトルを掴む (TOPへ) >>>





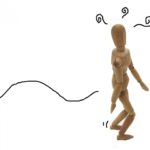





















この記事へのコメントはありません。