いま、介護業界の抱える最大の課題は、「高齢者の住まい」を巡る制度の大混乱です。
それは、大きく分けて三つあります。
① 高齢者住宅と高齢者施設(介護保険施設・老人福祉施設)の混乱
② 有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の混乱
③ 高齢者住宅に適用される介護報酬の混乱
この三つの混乱で生じている社会保障費の無駄は、「制度矛盾によるもの」「不正行為によるもの」を合わせると全国の介護費用総額の二割~三割、金額にして2兆円~3兆円規模に達します。この矛盾・不正を早急に改善しなければ、どれだけ介護報酬を上げても、砂に水を撒いているようなもので、介護サービスの向上や介護人材の労働環境の改善にはつながりません。
低価格の住宅型有料老人ホームやサ高住での囲い込みや、ナーシングホームによる訪問介護費の搾取など、高齢者住宅の巨額の不正事例については、他のところでも詳しく述べていますので、ここでは「制度矛盾」、特に介護保険施設に焦点を当て、想定される制度改定の方向性・未来について考えます。
① 介護保険施設の一元化
施設が整備された当初は、特養ホームは社会的弱者のための「要介護+要福祉」、老健施設は「要介護+在宅復帰」、介護医療院・介護療養型医療施設は「要介護+要医療」とそれぞれに役割が明確にされていましたが、現状をみると、その対象者の多くは重なっています。入院から在宅復帰のための中間施設と呼ばれた老健施設も、長期入所となっているところが多く、その対象者は特養ホームと同じです。介護医療院と介護療養型医療施設も、「廃止、統合、老健に一本化」と、名称を替えながら迷走を続けています。 いまや、介護保険施設が三つに分かれている理由は一つもありません。今後、介護保険施設の介護報酬は一本化される可能性が高く、在宅復帰のためのリハビリ、医療依存度の高い高齢者への医療対応については、個別施設、個別入所者に対する報酬加算で対応することになるでしょう。
② 特養ホームの自己負担の増加
現在の特養ホームは、実質的に「終の棲家」となっています。
ここで、問題となっているのが、民間の高齢者住宅との価格差です。全室個室のユニット型特養ホームは、同程度のサービスを提供する介護付有料老人ホームの半額程度で利用することが可能です。
その理由は、大きく分けて四つ。
○ 開設時に建物設備に対して数億円の建設補助が拠出されている
○ 社会福祉法人には、法人税・事業税・固定資産税などが非課税・減免されている
○ 指定人員配置はほぼ同じだが、介護報酬の単価(及び加算体制)には差がある
○ 特養ホームには独自の低所得者対策(特定入所者介護サービス費)がある
なぜ、特養ホームは、このように二重・三重に優遇されているかといえば、住宅対策・介護対策だけでなく、福祉対策・低所得者対策が一体的に行われているからです。実際、厚労省は、特養ホーム入所者には、在宅で暮らす要介護高齢者よりも、一人当たり年間180万円(月額15万円)の社会保障費が多くかかると発表しています。そのため、いまのユニット型特養ホームと同程度のサービス水準の介護付有料老人ホームは、特養ホームの基準額の二倍の月額30万円の費用がかかるのです。
現行制度では、独居の認知症高齢者や重度要介護高齢者を優先的に入所させるようにと指導されていますが、その優先対象者もこれからどんどん増えていきます。その需要・ニーズに合わせて、低価格個室の特養ホームを作り続けることは、財政的にも人的にも100%不可能です。
結果、同じ重度要介護高齢者でも、運よく特養ホームに入所できた高齢者と、それ以外の民間の高齢者住宅や自宅で生活する人との間に、受けられる社会保障の恩恵に大きな格差が生まれています。特に、ユニット型特養ホームは、一定以上の資産・収入の人しか申し込むこともできないという、老人福祉施設としては致命的な欠陥を抱えています。
そのため、特養ホームや老健施設の長期入所者に対する自己負担の上限は、「前年度収入+金融資産」を算定基準として、介護付有料老人ホームと同程度、最大で25万円~30万円程度に引き上げられることになるでしょう。
③ ショート・ミドルステイなど在宅支援機能の強化
現在、多くの地域で、不足しているものがショートステイ・ミドルステイです。
ショートステイは、主に家族の介護負担軽減のために利用されるもので、期間は1週間から2週間程度。一ヶ月に一度、二ヶ月に一度と定期的に利用する人や、冠婚葬祭などで家族が一時的に介護できない時のために利用されています。
一方のミドルステイは、3か月~6か月程度。定期的な利用ではなく、「脳梗塞で重度要介護となり自宅で生活できなくなった」「介護していた家族が骨折して入院した」など、生活環境を大きく見直す必要がある場合、その検討や環境整備のための時間的余裕を確保するために利用するものです。
このショート・ミドルのどちらも自宅で生活している要介護高齢者や家族が「イザ」というときに困らないために、また、できるだけ長く自宅で生活を続けるためにも不可欠なサービス・機能です。
そのために必要となるのが、現在の長期入所となっている介護保険施設の在宅支援機能の強化です。
それは、「高齢者住宅との役割の分離」「制度の公平性」という二つの視点から必要です。財政的にも介護保険施設を作り続けることはできないため、「運よく入所できた人だけの施設」ではなく、これを在宅高齢者にも恩恵があるように広く開放しなければなりません。
施設の本来の役割は「終の棲家」ではなく、病院と同じように、あくまでも一時利用のものです。そのため「ショートステイ」「ミドルステイ」については、低価格で利用できるけれど、その期間を超えると民間の高齢者住宅に移ってもらう、もしくは民間の高齢者住宅と同程度の費用負担になるといった、制度全体の公平性・効率性が求められることになるでしょう。
以上、ここまで、三回にわたって、予想される社会福祉法人の事業環境の変化について、「福祉機能強化の義務化」「営利法人との役割の分離」「老人福祉施設の未来」のポイントに分けて整理してきました。
「ここで挙げたことは、必ずそうなるのか」と聞かれれば、それはわかりません。
「そうはならない」と思う人は、笑い飛ばしていただいて結構です。 ただ、この「制度矛盾の解消」は、社会保障費削減の施策として、多くの国民が賛同する政策なのです。そのため、そこにメスが入った時点で、必ず行われることになるのです。
ただ、いずれも社会福祉法人にとって、その影響は「介護報酬の数パーセントのアップ・ダウン」といった軽易なものではありません。特に、事業基盤の乏しい新しい社会福祉法人にとっては、大きなダメージとなり、社会福祉法人の倒産・合併・統合が一気に進むことになるでしょう。
現在、老人福祉関連の社会福祉法人は、6700~6800程度とされていますが、あまりに小規模の事業者が多く、経営基盤もノウハウも安定していません。一部の法人は、公益法人を隠れ蓑にデタラメな運営を行っており、それが地域福祉の機能低下につながっています。特に、議員や天下り公務員のお財布代わりの社会福祉法人、薄っぺらい経営者気取りの社会福祉法人には、老人福祉の世界から消えるべきなのです。社会福祉法人の改革は必須であり、その結果、その数は三分の一~五分の一程度になるはずです。
これから社会福祉法人全体に対する視線は、確実に厳しくなります。「いまの社会福祉法人は本当に必要なのか」「やっていることは営利企業と何も変わらない」と言う視点で見られ始めていることに、気づかなければなりません。「不正をしていないから大丈夫」という話でもありません。十重二重に巻かれた優遇施策の中で、何も考えなくても、誰がやっても悠々と運営が続けられるような時代は終わるのです。
ただ、社会福祉法人は、営利事業ではありません。
薄っぺらい「勝ち組」になる必要はどこにもありません。
社会福祉法人は、大きく変動する福祉課題・介護課題に貢献できる事業体でなければなりません。
その福祉課題は、それぞれの自治体、それぞれの地域によっても変わってきます。
求められるのは高い利益ではなく、また「福祉の力」という曖昧なものでもなく、地域社会に貢献できるだけの体力と知識・技術、ノウハウです。その厳しい冬を超えられる社会福祉法人だけが、新しい春を迎えることができるのです。
【関連するリンク】
◆ 社会福祉法人は冬の時代を迎える (Ⅰ) ~福祉機能強化の義務化~ 🔗
◆ 社会福祉法人は冬の時代を迎える (Ⅱ) ~優遇施策の見直し~ 🔗
◆ 社会福祉法人は冬の時代を迎える (Ⅲ) ~特別養護老人ホームの未来~ 🔗


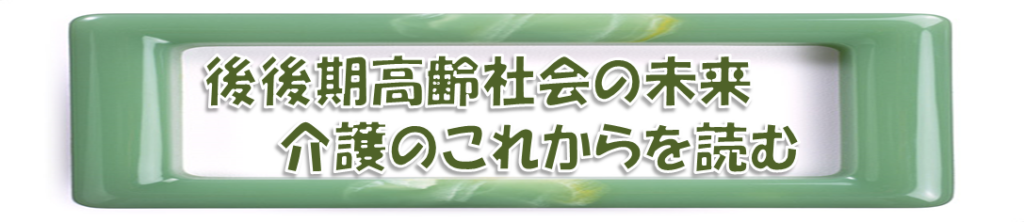















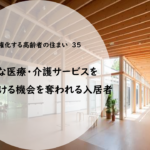









この記事へのコメントはありません。