社会福祉法人の理事長や特別養護老人ホームの管理者、またその団体の幹部と話をするときに、必ず伝えるのが、「これから社会福祉法人は冬の時代を迎える」ということ。「今でも、社会福祉法人の事業環境は厳しい」と訴えている人は多いのですが、残念ながら、これからより厳しくなることは間違いありません。社会福祉法人の事業環境が現行のまま維持される可能性はゼロです。
しかし、その危機意識は高くありません。
団体の施設長会で話をしても、「後後期高齢社会は、大変な世の中になりますね…」「社会福祉法人も安穏としてられませんね」といった、切迫感のない他人事のような立場・意見の人は多く、「危機意識を持っている」と話す理事長でも、「どのようなリスクが想定されるのか」「中長期的にどのような対策が必要か」「いま何をすべきか」までを、戦略的に検討できている法人は”ない”と言っても良いレベルです。
これは、介護報酬が上がる・下がるといったタイプの話ではありません。
もしかすると、介護人材確保のために全体の介護報酬は上がるかもしれません。しかし、それとは比較にならないほどの大きな波がやってきます。「介護・福祉を守れ」「介護報酬を上げてほしい」と右こぶしを振り上げることは必要ですが、同時に左手では、来るべき厳冬の時代を見据え、緻密に生き残りの戦略を立てていかなければなりません。そうしないと事業そのものが崩壊し、莫大な借金だけが理事長や理事個人に圧し掛かってくることになります。
もう、その兆候は見え始めています。
ここでは、三回に渡って、社会福祉法人の経営環境の変化とその対策について考えます。
社会福祉法人の福祉機能の強化・透明性の確保
「認知症による近隣トラブルが発生しているが、興奮し話し合いに応じない」
「長男の虐待が強く疑われるが、当の要介護の母親が庇う」
「親は認知症で徘徊、同居する娘がうつ病で自殺をはかる」
老人福祉の現場にいると、通常の契約に基づく介護サービスだけでは対応できない、答えのない難しいケースに遭遇します。介護保険制度の発足で、老人福祉の役割が小さくなったわけではありません。要福祉の困難ケースは、介護保険がスタートした2000年よりも多様化・深刻化し、その数も比較にならないほどに増えています。
いま、社会問題となっているヤングケアラーも「介護サービスを利用すればよい」「情報提供が必要」という単純な話ではありません。その多くはシングルマザーや貧困、保育とのダブルケア、精神的な疾病など、それぞれに外部からは見えにくい複合的な福祉課題が存在しています。同様に、家族による介護虐待の背景には、不本意な介護離職や貧困、引きこもりによる8050問題など、複数の社会問題が絡み合っています。
社会福祉法人の本来の役割は「介護サービスの提供」ではなく、これら申請に基づく介護保険だけは対応できない「要福祉高齢者」への対応です。このようなケースは、独居認知症の問題を含め、本人・家族がそうとは気づいていないケースが大半であり、社会から閉ざされたところで根が深くなっていきます。そこに「こうすればいい」といった正しい答えはなく、長期継続的な支援・サポートが必要となるため、効率性・収益性を重視する営利事業では対応できません。そのため、社会福祉法人には非営利事業として、高額の補助金支出や税制優遇が行われてきたのです。
しかし、その本来の目的・役割を忘れ、一般の営利法人と競うように介護サービス事業に傾倒している社会福祉法人が増えています。介護虐待やネグレクトなどの要福祉の高齢者には「措置入所」という行政措置による特養ホームへの緊急入所も残されていますが、「措置はトラブルになるから嫌だ」と受け入れを拒否する事業者も少なくないと聞きます。
更に、一部の社会福祉法人は地方自治体の利権の温床となっています。
理事長が地方議員、その妻や息子、天下り公務員が特養ホームの施設長や事務長となり、一千万円以上という高額所得者も少なくありません。その給与・報酬の総額は全国で年間数百億円規模に上るとされており、そのしわ寄せで、介護や福祉に精通した経験豊かな有資格者の介護福祉士や社会福祉士の給与が上がらないのです。何もできない議員理事長、素人施設長のもとで、業務負担だけが重く現場に圧し掛かっているというのが現実です。幹部が議員や天下り公務員のため指導監査の目も行き届かず、ガバナンスが効かないため、社会福祉法人の資金流用や介護スタッフによる虐待などが横行している法人もあります。
口先で「福祉の推進」を訴えている行政や議会が、自らの利権のために、地域福祉を私物化し、その質の低下、崩壊を招いていると言っても過言ではありません。
老人福祉施設の福祉機能の強化・義務化
これまで「介護・福祉」と言えば何でもありの状況の中で、その矛盾や課題が覆い隠されてきました。しかし、介護保険財政が極度にひっ迫する中で、その制度矛盾や一部天下り法人のデタラメっぷりは、大きな社会問題となるでしょう。残念ながら、適切に運営している全国の社会福祉法人さえも、厳しい視線に晒されるということです。
まずは、想定される社会福祉法人に対する福祉の機能強化策について整理します。
① 要福祉高齢者への相談・対応の義務化
あと10年で、認知症発症率が顕著に高くなる85歳以上の高齢者が1000万人を突破します。
一人暮らしの認知症高齢者の徘徊やゴミ屋敷、失火などの近隣トラブル、不本意な介護離職による介護虐待やネグレクトは相当数に上るでしょう。現在、これらの福祉ケースの相談先は、地域包括支援センターや行政の福祉事務所となっていますが、どちらも介護サービスを持っていないため、表面的な調整に留まり、一時避難や措置入所などの実務的な対応ができません。そのため、福祉ケースの相談・対応は、エリア単位で社会福祉法人に義務付けられることになるでしょう。これら地域福祉課題にどのように貢献しているのか、社会福祉法人としてその役割を果たしているか、その実施状況について、厳しく報告を求められることになります。
② 特養ホームの要福祉高齢者の受け入れの義務化
二つ目は、特別養護老人ホームの要福祉・困難ケースの受け入れの義務化です。
特別養護老人ホームは、実質的に要介護高齢者の住まいであり、「高齢者住宅」との役割が不明瞭になっていますが、その本来の役割は老人福祉施設です。「介護サービス」だけでは対応できない「要福祉高齢者」のための施設です。しかし、その基本を忘れ、「困難ケースはお断り」と実質的に受け入れを拒否している特養ホームは少なくありません。特に、ユニット型特養ホームはその傾向が強いと言われています。
最近は、「誰でもすぐに入居可」という低価格のサ高住に入居者が流れ、特養ホームの待機者が少なくなっています。このような囲い込み型の貧困ビジネスは不正の温床となっており、課題は多いのですが、「行き場のない高齢者」「緊急避難が必要とされる高齢者」に、社会福祉法人、特養ホームが向き合ってこなかったという背景があることは事実です。
そのため市町村の中には、「特養ホームの申し込みは自治体が一括して受け付け、入所先を調整する」というところが増えています。それは全国に広がります。それによって緊急避難が必要な福祉ケース、介護虐待などの困難ケースの受け入れも義務化されることになります。これからは従来の「措置制度」ではなくても、実質的に自治体からの入所依頼に基づいて入所を受け入れることになり、よほどの事情がない限り、断ることはできないでしょう。
③ 施設長・管理者資格の義務付け
三つ目は、施設長・管理者資格の義務付けです。
社会福祉法人は、特別養護老人ホーム・養護老人ホームなどの福祉施設だけでなく、通所介護・訪問介護などにおいても、福祉ケースを優先的にサポートする責任・義務を負います。それを行うためには、介護サービスだけでなく、福祉ケースの高い知識・技術、ノウハウ・経験が必要となります。福祉施設の施設長や管理者には、介護福祉士や社会福祉士、ケアマネジャーなどの有資格者であると同時に、福祉現場での実務経験が五年以上といった経験が必須となります。もちろん、その公開義務も合わせて行われることになります。
④ 理事長・理事・施設長報酬の開示
最後の一つは、理事長や理事、施設長報酬の開示です。
「介護報酬が低いから介護スタッフの給与が上がらない」と言われている一方で、社会福祉法人の一部では、議員理事長とその家族理事、また地域・経験のない天下り施設長の給与が一千万円以上というケースも目立っています。事業に対する責任の重い理事長や管理者が高い給与・待遇を得ることは当然ですが、公益法人であるため、それが適切なものであるか否かは、外部及び、スタッフに公表されなければなりません。③で述べた通り、理事長や理事、管理者の資格だけでなく、その責任や役職、報酬の有無の額についても、開示・公表が求められることになります。
以上、「福祉機能の強化」という視点から、四つのポイントを述べました。。
これから、社会福祉法人は、本来の役割である福祉機能の強化や運営上の透明性の確保は不可欠であり、「社会福祉法人はその責任を果たしてきたのか」という批判が高まるにしたがって、本来の役割がより厳しく求められることになります。そうなると対応の難しい認知症高齢者の増加だけでなく、家族とのトラブルも増えることが予想されます。これまでの「福祉の力で」といった曖昧な美辞麗句ではなく、家族のカスハラや認知症トラブルへの対応強化など、スタッフを守るためのリスクマネジメント対策の強化は必須です。それができない事業所は、スタッフがどんどん逃げ出し、事業の継続が困難になるでしょう
続く >>> 社会福祉法人は冬の時代を迎える (Ⅱ) ~優遇施策の見直し~
<<< 介護のニュースを読む、ベクトルを掴む (TOPへ) >>>





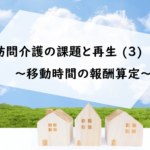


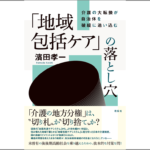


















この記事へのコメントはありません。