社会保障格差の時代へ 日本社会の底が抜ける(中)より <<<続く
ここまで、社会保障格差を生む要因として、「世代間格差」「地域間格差」を上げてきた。
「国民皆保険・皆年金」の制度が崩壊しつつあると言ってよいだろう。
この世代間格差、地域格差に加えて、もう一つ、要因として挙げるのが「雇用環境の変化」による格差だ。
バブル崩壊後の雇用環境の激変
社会保障格差の時代へ 日本社会の底がぬけるとき(上)🔗で、人口のアンバランスによる社会保障の世代間格差を上げたが、中でも、スポット的にその影響を最も強く受けるのが、「氷河期世代」「リストラ世代」だ。
2004年に労働者派遣法が施行され、企業側への規制が緩和されたことで派遣社員、つまり非正規での雇用が増加した。「それぞれの生活リズムに合わせて自由な働き方ができるようになる」とそのメリットが喧伝されたが、実際は、企業のリストラ対策、人件費削減対策であったことは明らかで、同一労働であっても、正社員に比べて圧倒的に給与・待遇が低く、さらに雇用が不安定であるというデメリットばかりが表面化した。
同時期の1990年代後半から2000年代にかけては、40代~50代が解雇・退職勧告の対象となった。常勤・正規の仕事に就くことができず、やむなく非正規・派遣労働にならざるを得なかったという人たちも多い。結果、非正規雇用の割合は、1990年の20%から2000年前半には4割と二倍となり、その比率は、2025年現在も変わっていない。その半数は、「正規で働きたいけれど…」という不本意非正規労働だ。
1970年~1983年に生まれた氷河期世代は、現在42歳~55歳になっている。不景気でリストラの嵐が吹き荒れた1992年~2005年に45歳~55歳だったリストラ世代は、今年65歳~75歳と高齢者の仲間入りをする。
なぜ、この世代の雇用環境が社会保障の格差に直結するのかと言えば、日本の社会保障制度は、「常勤雇用・終身雇用・年功序列」の日本型雇用形態のサラリーマンを土台として作られているからだ。
バブル崩壊までの高齢者は、高校や大学を卒業後、同じ企業で40年働き、住宅ローンや子育てが終わった時点で、ある程度のまとまった退職金をもらい、毎月20万円程度の年金と、退職金の取り崩しで生活することができた。そのような働き方、老後設計が一般的だったと言える。
しかし、これから75歳の後期高齢者に突入するリストラ世代は、40代、50代という最も給与水準が高く、かつ住宅ローンや教育費の支払いがピークとなる働き盛りの時に、会社が倒産し、人員整理で解雇されている。割増退職金を食いつぶしながら、低賃金のパート・アルバイトで何とか食いつないできたという人も多いだろう。
これは氷河期世代も同じだ。
彼等が高校、大学を卒業して就職した時代、新卒者の就職内定率は 1995年には60%台に下落し、2002年には55.1%と最低を記録、2006年に63.7%となるが、リーマンショックの2011年には再び57.6%と六割を切る。この世代の大学生の就職率は69.7%と他の世代の平均(80.1%)よりも10%以上低いことが知られている。望む仕事に就くことができず、キャリアアップもできず低賃金、不本意なまま非正規を続けている人は50万人、未婚率も高く、引きこもりや長期間にわたり求職活動をしていない人を含めると100万人になるといわれている。
高齢者の三割は必要な医療・介護サービスが受けられないという現実
不本意にもバブル崩壊の波にさらわれ、「失われた20年」と呼ばれた経済低迷期に、非正規雇用のまま過ごさなければならなかった人達の多くが直面するのが「老後の貧困」だ。
「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢基礎年金(国民年金)の平均年金月額は5.6万円、厚生年金は14.5万円とされているが、受給者2660万人のうち10万円未満の人が1396万人と半数以上、5万円以下の人も16%に上る。同様に、70歳以上の夫婦世帯の平均貯蓄額は1923万円とされているが、単身世帯ではゼロ・もしくは100万円未満というほとんど蓄えのない人の割合も32.1%になる(夫婦世帯でも2割)。
「低い年金額=預貯金ゼロ」というわけではないが、その多くはリンクする。現在でも、低年金低資産の割合は高齢者の二割、10年後に氷河期世代が高齢者に入ると三割を超えるだろう。彼らは、年金だけでは生活することができず、65歳になっても70歳になっても75歳になっても、身体の動くうちは働かざるを得ない。ただ、問題は80歳、85歳を超えて、介護や医療が必要になったとき、特に、認知症や重度要介護になって、自宅で生活できなくなった時にどうなるのかだ。
預貯金ゼロ(もしくは100万円未満)、年金月額10万円の単身高齢者の例を挙げてみる。
介護保険や後期高齢者医療の保険料もこれから上がっていく。住んでいる都道府県・市町村によって違いはあり、低所得者に対する減額措置があるとしても、合わせて最低一万円以上は支払う必要があるだろう。それ以外にも賃貸住宅に住んでいる人は家賃が必要になるし、持ち家の人には固定資産税がかかる。手取り額が八万円以下となると、ギリギリの生活にならざるを得ない。
介護や医療が必要になれば、一割負担が発生する。高額療養費、高額介護サービス費の減額制度を使っても、それぞれ1.5万円で合わせて三万円(高額介護合算療養費制度でも年間31万円)、それ以外にも紙おむつなどは全額自費だ。
更に問題は、要介護状態・認知症が重くなって、自宅で生活できなくなった時にどうするのかだ。彼等には入所・入居できる老人ホーム・高齢者住宅は、極めて限られているからだ。
介護付有料老人ホームは、最低でも月額20万円~25万円は必要となるため対象外。最近は、低価格を売りにした囲い込み型の住宅型有料老人ホームやサ高住が増えているが、これも最低でも15万円~20万円は必要だ。「生活保護受給者でも入居可」というところもあるが、これは「医療介護の自己負担のない生活保護だから入居可」であって10万円程度の年金受給者は対象外だ。認知症高齢者専用のグループホームがあるが、これも20万円程度なので、入居することはできない。
そう考えると、残された道は特別養護老人ホーム(特養ホーム)しかない。
特養ホームは老人福祉施設であり、低所得者対策がある。ただ、この特養ホームは従来の多床室型(四人部屋など)とユニット型個室に分かれており、低所得者が入所できるのは多床室型に限定されている。しかし、厚労省はこのユニット型特養ホームを全体の七割にするという目標を掲げており、いまでも全特養ホームの約半数はユニット型となっている。
「特養ホームの待機者が50万人を超えた」などと報道されたことがあったが、待機者(入所希望者)が殺到しているのは多床室型であり、低所得者が入れないユニット型特養ホームの一部は待機者ゼロというところも出てきている。
つまり、重度要介護や重い認知症になって、介護機能の整った老人ホームや高齢者住宅に入りたいと思っても、二割・三割の低資産・低所得の高齢者は、必要な介護を受けられず、最後の砦となる老人福祉施設の特養ホームへの道さえも極めて狭いものとなっているのだ。
1 ユニット型特養ホームの課題 ① ~あまりに非効率~ 🔗
2 ユニット型特養ホームの課題 ② ~高級老人ホームの半額~ 🔗
3 ユニット型特養ホームの課題 ③ ~福祉施設の役割が崩壊~ 🔗
4 ユニット型特養ホームの課題 ④ ~福祉の利権化~ 🔗
では、社会保障の格差による勝ち組は誰だろう。
この世代の雇用環境が社会保障の格差に直結する理由は、日本の社会保障制度は、従来の日本型雇用形態である「常勤雇用・終身雇用・年功序列」のサラリーマンを土台として作られているからだと説明した。
その中でも最も優遇されているのは、公務員や教職員、金融機関など大手企業を新卒から定年退職まで勤め上げたサラリーマンだ。彼らは退職時に数千万円単位の退職金と、毎月20万円に近い年金を受け取ることができる。述べた、介護付有料老人ホームは選び放題で、社会保障費をふんだんに使った老人福祉施設のユニット型特養ホームに優先的に入所できるのも彼らだ。
これを不条理だと言っているわけではない。年金は保険であるため、自分が支払った保険料に合わせて受け取る額が変わってくるのは一つの考え方として間違ってはいない。ただ、雇用環境が激変し、不本意な非正規雇用が激増する中で、社会保障の格差を抑えるためには、「常勤雇用・終身雇用」ではなく、低年金の高齢者でも公平に利用できる医療・介護制度に変更しなければならなかった。しかし、ユニット型特養ホームの例を見てもわかるように、厚労省は、自分達公務員が最もそのメリットを享受できる、使いやすい社会保障制度、医療介護制度になるように維持・強化してきたのだ。
社会保障の格差社会に起きること
ここまで、社会保障の格差を生む、「世代間格差」「地域格差」「雇用格差」という三つの格差について述べてきた。その格差による被害を受けるのは医療介護が削減される高齢者だけではない。20歳~64歳までの勤労世代も、消費税、住民税、固定資産税に加え、介護保険料、健康保険料などの重い社会保障の負担を背負うことになる。しかし、全体の二割、三割になる低資産・低所得の非正規労働者は、重い負担を背負わされ、しぼり取られるだけで、自分が要医療・要介護高齢者になった時には、必要な医療・介護を受けにくい、受けられないという悲惨な状況になるのだ。
日本が「失われた30年」と呼ばれた長期の経済低迷から復興できなかった理由は、大きく分けて二つある。一つはバブル崩壊後の短期経済対策が不十分だったこと、もう一つは、少子高齢化によって、人口のアンバランスが拡大したにも関わらず、社会保障制度の改革が遅れ、高齢者の医療介護費の増加が、経済成長・復興を妨げてきたことだ。
この二つの要因は、連関している。いま、ロボットやAIなどの新産業の勃興によって、ようやく景気が上向いてきたように見えているが、それは長続きしない。このままの制度が続けば、2040年には税収の七割、八割が社会保障費に費やされることになるため、経済にお金が回せないからだ。言い換えれば、社会保障制度改革なしに経済の立て直しはできないし、また経済の立て直しなしに、社会保障制度の改革もできないのだ。
しかし、その抜本的な対策を放置したため、格差の拡大だけが進んできた。それは収入格差、資産格差だけでなく、子育て、教育格差に及び、行政サービスである医療介護さえも、格差拡大の一途を辿っている。政治家は、長期的な展望のないまま「介護福祉の充実」「消費税減税」「保険料の値下げ」を叫んでいるが、彼らの目には目先の選挙だけで、この格差の拡大や五年先に日本がどうなってしまうのかも見えていないだろう。
いま、自民党・立憲民主党・公明党によって、「国民年金の底上げに厚生年金の積立金を取り崩す」という合意がなされたが、これも「格差解消」「低年金の高齢者のため」という単純な話でない。所得税がかかる「103万円の壁」というものが話題になったが、高齢者の年金には「80万円の壁」というものがある。介護保険料や高額療養費、高額介護サービス費などは、80万円を超えるか越えないかによって段階が変わるからだ。いまの国民年金の満額は831,700円(月額69,308円)となっているが、未納期間によって、年額80万円を切る人の割合が多い。だから、ここを割り増しして、保険料支払いを上げ、高額介護・高額療養費の支出を抑えるのだ。収入が数万円増えても、医療介護の支出が二倍・三倍に増えることになる。
この社会保障の格差の拡大は、セーフティネットが破れることを意味している。
これから「亡くなったまま数か月放置」という高齢者の孤独死は日常的なこととなる。近隣の人間関係の薄い都市部でそれは顕著なものとなるだろう。要介護3になってもお金がないため、施設にも入れなければ医療にもかかれない。週に一回、二回程度の訪問介護がやってきて、死亡している高齢者を見つけるというくらいになるだろう。
認知症高齢者は更に悲惨だ。社会福祉法人の福祉機能が低下しているため、独居の認知症高齢者は放置されたままになる。寒空に便失禁をしたまま、半裸で徘徊する認知症高齢者が街に溢れ、認知症高齢者の自動車事故や万引き、ゴミ屋敷や失火による火災が激増、感染症や食中毒となどの公衆衛生も崩壊し、それは社会全体を覆っていく。
50代、60代になれば、自分の老後がどのようになるのか見えてくる。高額の宝くじでも当たらない限り、そこから資産や所得を増やすことはできない。モラルハザードを引き起こし、詐欺や闇バイトに手をそめる中高年、自暴自棄になって無差別殺人や通り魔と言った事件も増えるだろう。
この「リストラ世代」の子供が「氷河期世代」だ。親が低所得低資産で介護が受けられなければ、子供が介護するしかない。仕事を辞めて無職になるか、また非正規になってその格差のスパイラルは世代を超えて連鎖していく。
社会保障の格差の拡大は医療介護問題ではない。
日本社会の底が抜けるということだ。
残念ながら、そう遠い未来の話ではない。ただ、全国民が公平・公正に利用できる医療介護政策の抜本的な改革を行う時間はないし、事ここに至っても、政治家にも厚労省にもその気はない。すべての対策があまりに遅すぎるのだ。残された道は、介護サービス事業者も高齢者も若者も、それぞれが貧困に陥らないように自衛することだけだ。


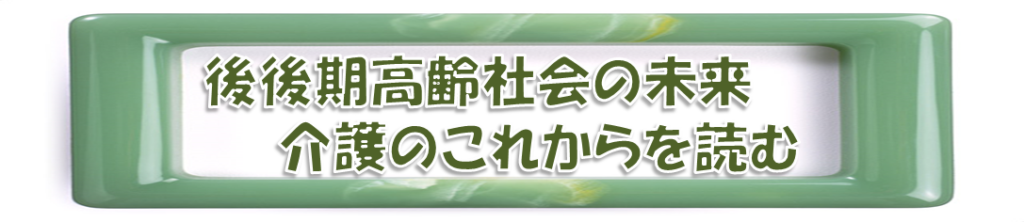
















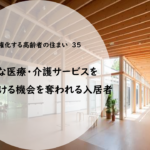








この記事へのコメントはありません。