介護人材不足解消の処方箋 Ⅰ ~介護看護の紹介・派遣業の禁止①~ >>>から続く
一般的な営利事業の場合、商品・サービスの価格は市場(需要と供給)によって決まり、それは常に変動する。一方の介護サービス事業は、民間経営の営利事業でありながら、その収入の根幹を公的な介護保険制度が担っているという、他に類例のない極めて特殊な事業だ。
介護サービス事業者が、「この介護報酬では優秀な介護人材が集まらない」と訴えるのは当然だが、少子高齢化による人口のアンバランスが拡大する中で、その財源となる保険料の値上げや増税(消費税、固定資産税、住民税)は容易ではない。
まず、ここで考えたいのは、介護報酬は適切に介護スタッフに適切に配分される仕組みになっているか、それを阻害する要因がないのかだ。
介護看護の派遣・紹介業に流れるお金は数千億円規模
「介護系職種の有効求人倍率が四倍を超えた」
「介護系職種の有効求人倍率は、一般産業の四倍に…」
新聞やニュースで【有効求人倍率】という言葉がでてくるが、これはハローワークに登録された「有効求人数」を「有効求職者数」で割って算出する。これまで失業率などとともに、景気動向、特に労働市場の動向を示す重要な指標として用いられてきたが、最近では、その数値の持つ意味や確かさは変わってきている。なぜなら、この求人活動、求職活動の主戦場は、事業者・求職者ともにハローワークではないからだ。
述べたように、「ハローワークで求人をしてもひとりもスタッフが来ない」「介護人材が絶対的に不足している」という一方で、実際の事業経営をみると、人材確保が極めて逼迫している都市部においても、経営・サービスの維持に必要な介護職員は確保されている。
その背景にあるのが、派遣職員や人材紹介業の増加だ。
他の業界では、正規職員と比べ非正規労働の待遇の悪さが問題となっているが、介護業界では慢性的な人材不足を背景に、派遣職員の給与が上がっている。介護業界で働く派遣労働者の実数は報道されていないが、「令和5年度 介護労働実態調査」によると、派遣労働者を受け入れている事業者は14.2%。ただ、地方の小さな市町村では派遣事業者がいないことを考えると、大都市部では二割~三割程度になるのではないかと推定される。特に、介護付有料老人ホーム、グループホームその割合も大きくなっており、介護職員の半数以上が派遣職員というところもある。
派遣は、勤務体系やシフトも自分の自由に決められて、イヤになればいつでも辞められる。そのしわ寄せや重い責任だけが、正規職員に圧し掛かるという逆格差が生まれているため、「正規職員なんてバカバカしくてやってられるか…」と介護サービス事業所を退職し、派遣会社に登録する介護福祉士や看護師が激増しているのだ。
同様に、介護の人材紹介も活発化しており、一人の正規職員を紹介してもらうと、その紹介料は年収の二割~三割が相場だ。例えば、常勤で年収400万円の介護職員を一人紹介してもらうと100万円近くかかる。全国介護事業者協議会のアンケートによると、加盟事業者のうち、有料職業紹介会社からの紹介による職員の採用を行っているところは、全体の36%に上るとしている。それは、ハローワークや求人広告程度では人材確保ができないが、「有料の紹介業者を通せば、確実に応募者が見つかるからだ。つまり、今の介護求職者の多くは、ハローワークに行くのではなく、有料の紹介業者に登録しているということだ。
厚労省のまとめた【職業紹介事業の事業報告の集計結果(令和五年)】によると、その紹介料の総額は、介護関連職員だけで年間450億円、病院なども含めた看護師を含めると1000億円をこえる。最近、インターネットでもテレビでも、介護看護の派遣や紹介業に特化した企業の広告を頻繁に目にするだろう。それだけ儲かっているからだ。
紹介業+派遣業者に流れるお金は、少なくとも数千億円の規模になるだろう。その原資は本来、正規の介護スタッフに支払われるはすだった介護報酬であり、その費用だけで介護報酬総額の2~3%に上る。それだけ介護サービス事業所の利益が削られ、正規職員として頑張っているスタッフの給与が抑えられているということだ。
「介護派遣は、この人手不足を補うための手段として、一定の役割を果たしている」
「紹介業者に頼まなければ職員が集まらない」
という人がいるが、それは発想が逆だ。介護サービス事業は、繁忙期と閑散期がある事業でも、受注の増減によって一時的に多数の人材が必要となる事業でもない。非正規の派遣業が必要な業態・業界ではなく、積極的に「正規職員ではなく、派遣労働者、紹介労働者を使いたい」と考えている事業者は一つもない。介護看護人材はいるのに、派遣業者や紹介業者に巨額の費用を支払わなければ、集まらないというだけだ。
派遣・紹介業が介護業界に及ぼす悪影響
派遣紹介業が介護業界に及ぼす悪影響は、金銭的な問題だけではない。
令和2年度老人保健健康増進等事業「在宅介護事業者における派遣労働者の活用実態と適切な活用・キャリア形成支援のあり方等に関する調査研究」によれば、事業者や介護現場が、積極的に派遣・紹介業者を受けいれているのではないという実態が浮かび上がってくる。
◆ 紹介手数料に見合う人材が紹介されない
◆ 採用した人材の抱える問題が、入職後に明らかになる
◆ 紹介を受けた人材が、入職後6か月以内などの短期で離職する
有料紹介業といっても、その多くは紹介業者自らが個別の求職者と面接をして、その適正を見極め、責任をもって介護サービス事業者に紹介をしているわけではない。「聞いた話と全然違う」「前事業所で虐待していた」などの問題が明らかになることもあるという。それでも、紹介業者に何も責任も生じない。
有料職業紹介会社や派遣労働者に支払う余裕があれば、常勤職員の処遇改善に回すべきとの反発が職場内に生じ、会社への不信感から辞めていく人も多いという。その不平不満の矛先は、紹介されて入職した介護職員にも向けられる。紹介による介護職員は、新入社員ではなく、高度な知識・技術をもつ「即戦力」を求められる。「えっ? そんなことも知らないの?」「全然、仕事できないじゃない…」となり、一定期間が過ぎると、早々に退職してしまうのだ。
派遣労働の増加は、サービス低下にもつながっている。
この派遣労働を使っている多くの事業者から聞く言葉が、「法人・事業所への帰属意識が低い」というものだ。それも当然のことだと言える。正職員であれば、積極的に意図していなくても、「自分の働く事業所のサービスを向上させたい」「利用者・家族から高い評価を受けたい」と考えるだろう。しかし、派遣労働者には、組織としてこの帰属意識を持たせることはできない。彼らはどこにも属していないからだ。
最大の問題は、チームケアの崩壊だ。
介護や看護という仕事は、「その時間内に言われたことだけやればよい」という単純作業ではなく、また個々人の個別作業でもない。知識・技術が必要な専門的な仕事であり、交代勤務の中で連携、連絡を土台としてチームとして働いている。「Aさんのふらつきが気になる」「Bさんの車椅子がガタガタしている」「薬が飲まれていない」といった、個々人が気づいた事故やトラブルの種を報告、相談して、チームとして共有していかなければならない。
しかし、派遣職員には、その帰属意識はない。ある施設長に言わせれば、学生アルバイトのほうが帰属意識も仕事に対する責任感も強いという。言われたことしかやらないというより、自分は派遣職員なので「言われたことしかやってはいけない」「責任になるようなことはしてはいけない」「事故やトラブルは自分には関係ない」と考えているからだ。
事業者側は、派遣職員も正規職員と同じだと考えているが、仕事や働き方に対する意識は根本的に違うのだ。そうなると、チームケアどころか、連携や連絡がとれなくなり、注意をすると、すぐに来なくなってしまう。「派遣がいないと困る…」と注意もできないため、正規職員からの不平不満がたまり、サービスの質は一気に低下することになる。
これは、「派遣や紹介業を使っていない事業者には関係ない」という話ではない。
このままいけば、新卒者でさえも紹介業者に登録し、多くの事業者で介護報酬の10%以上の紹介料や派遣料を事業者に支払わなければ、介護人材が確保できない時代になるだろう。
それが、介護業界のあるべき姿だろうか。述べたように、介護サービス事業は、その収入の根幹を公的な介護保険制度、税金や保険料が担っているという、他に類例のない極めて特殊な事業だ。このまま放置すれば、間違いなく介護の紹介比率、派遣比率は伸びていく。介護報酬を上げたところで、紹介業者や派遣業者が儲かるだけで、いま介護人材不足が解消されないという意味がわかるだろう。
この問題は、高齢者住宅の入居者紹介業者の問題と類似している。
介護報酬が介護職員の給与・待遇に還元されず、外部に流出しているということだ。
紹介業や派遣業は、「囲い込み型高齢者住宅」などの不正事業者が人材不足でつぶれない一因にもなっている。訪問介護でも「紹介・派遣を受け入れている」というところがあるが、通常の訪問介護ではありえない。派遣や紹介に手数料を支払えば採算がとれないからだ。すべては囲い込み型高齢者住宅併設の訪問介護だ。
囲い込み高齢者住宅では、詐欺罪に該当するような多くの不正が行われており、まともな介護看護スタッフは働いていない。それでも巨額の利益がでているため、高額の紹介・派遣費用を支払って訪問介護をかき集めているのだ。
紹介業、派遣業がなくなっても、優良な介護サービス事業者や介護職員は何一つ困ることはない。紹介業、派遣業がなくなれば、給与・待遇・労働環境の悪い介護事業者は潰れる。それが介護業界のあるべき姿だ。
その上で「介護のプロに相応しい介護報酬を…」と求めない限り、劣悪な介護の労働環境も給与もかわらないのだ。


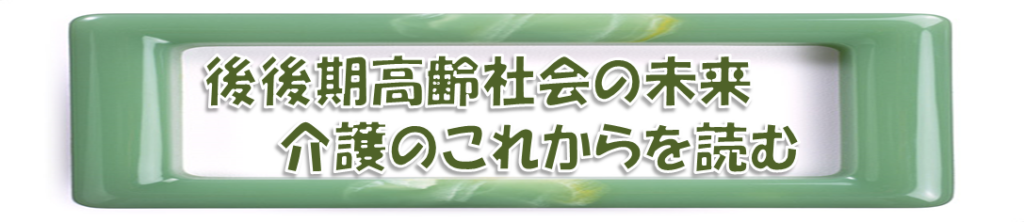

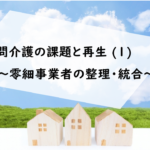













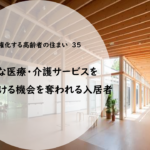









この記事へのコメントはありません。