ここでは、介護休業制度の実際の取得例について、解説していきます。
まずは、「介護休業取得のポイントⅡ🔗」で述べた、骨折や脳梗塞などで突然入院し、その後のリハビリで、自宅に戻ることのできた事例について紹介します。
突然の介護問題の発生
私は五二歳。とある中堅の食品工場で、検品課の課長をしている。
妻と高校生と中学生の子供の四人家族でマンション暮らし。実家は車で2時間ほどの距離にあり、父が亡くなった10年前から78歳になる母が一人で生活している。
ある日、仕事中に妻から「お義母さんが家の中で転倒、骨折して入院した」と電話。慌てていて詳しいことはまだわからないという。先に妻が病院に行ってくれたので、仕事が終わってから病院に駆けつけ医師から説明を受ける。
左大腿骨骨折で2~3週間程度の入院。手術は成功したが、年齢的に介護が必要になる可能性が高いとのこと。
会社の同僚の中でも「独身の弟が介護離職した」「親の介護で妻と揉めている」といった話題も多くなっており、「うちも、そろそろか」と考えなくもなかったが、元気に手芸教室やボランティアに出かけていたこともあり、まだ先のことだろうと高をくくっていた矢先のことだった。
考えごとをしていて、階段を踏み外したとのこと。
元気をなくし、「迷惑かけてごめんね」と涙ぐむ母。
上司の製造部長に相談し、事情を説明し一日有給をもらう。
翌日、遠方に住む姉がやってきて、これからのことについて相談するも、義母の介護を抱えており、戻ってくることは難しいとのこと。妻も近くの会計事務所で仕事をしており、私もサラリーマンのため介護に専念できる状況にはない。
マンション住まいのため、母のために一部屋空けると子供二人(娘と息子)を同室にせざるを得ない。近くにアパートを借りることや介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅なども考えたが、母は年金額がそれほど多いわけではなく、また私も姉も、まだ子供にお金がかかる年齢であり、毎月、多額の金銭的援助ができるわけではない。預貯金の額もそれほど多くなく、今から取り崩して生活すると、将来破綻することは目に見えている。あれもダメ、これも難しい、これからどうなるのか…と考えると、不安ばかりが大きくなり、眠れないまま仕事に向かった。
上司・人事に相談
翌日、出社すると上司の製造部長に呼ばれ、事情を簡単に説明する。
私だけでなく「親の介護」に関する勤務調整や相談は増えているらしい。「とりあえず、人事に相談してみてはどうか」と言われる。その時は「親の介護問題を人事に相談しても…」「下手に相談するとかえって…」と思ったが、部長がその場で人事部にアポイントを入れてくれ、翌日、本社へ向かった。待っていてくれたのは、食品工場の人事担当者ではなく「人事課 介護担当相談員」という肩書の出雲さんという女性だった。
出雲さんが聞いていたのは「母親が転倒、骨折して入院。介護が必要になる可能性がある」という情報のみ。何を話せばよいのか、また会社にプライベートな問題を、どこまで話をすればよいのかと戸惑ったが、開口一番、「プライベートな情報については秘密厳守します。希望されない限り、人事にも反映されません」と言ってくれたことから、張っていた肩が少し楽になった。
出雲さんは社会福祉士とケアマネジャーの資格を持っており、病院や介護現場での相談経験も豊富らしい。母の現状や病院の先生からの話、家に引き取れないこと、妻も姉も介護できないこと、子供のことやお金のこと、今後どうなるのか不安に思っていること、どうすればよいかわからないことを、思いつくままに話をした。
介護に対する経験も知識もないため、頭の中が混乱したままの支離滅裂な話だったが、彼女が上手く聞き取ってくれたことで、現状の問題点を整理することができた。
◆ 一人暮らしの母が転倒・骨折して介護が必要になるかもしれない
◆ 妻も私も仕事があり、姉も遠方であるため介護できない
◆ 今、住んでいるマンションに、母をひきとることは難しい
◆ 実家は築50年の一戸建てで要介護の高齢者には向かない
◆ 預金1000万円程度、年金月13万円程度、長期的・定期的な金銭援助は難しい
子供としてできる限りのことをしてやりたいが、いまの自分に何ができるのか、何をすればいいのか、わからない。そういうと、いくつかのアドバイスをいただいた。
① リハビリをきちんと行うこと
アドバイスの一つは、早くからきちんとリハビリを行うということ。
以前は、高齢者が大腿部骨折や脳梗塞になると、そのまま寝たきりになる人が大半だったが、最近では、早期にリハビリを行い、生活環境さえ整えば、以前と変わらず自宅で生活できるようになる人も多いという。リハビリ専用の病院も増えており、今の病院から退院後、一ヶ月~二ヶ月程度入院して集中的にリハビリを行うことができる(そういえば、病院の先生からもリハビリの話がでたが、要介護になるというショックでよく聞いていなかった)。ただ、母本人が一番ショックを受けており、認知症を発症するリスクもあるので、可能な限り面会に行き、「心配ないよ」「頑張ってリハビリしよう」と不安をやわらげ、励ますようにとアドバイスを受ける。
介護休業制度の取得事例 Ⅰ ~骨折・入院から自宅復帰~ (下) へ続く<<<
>>>>新連載 介護離職をしない、させない社会へ (TOP)

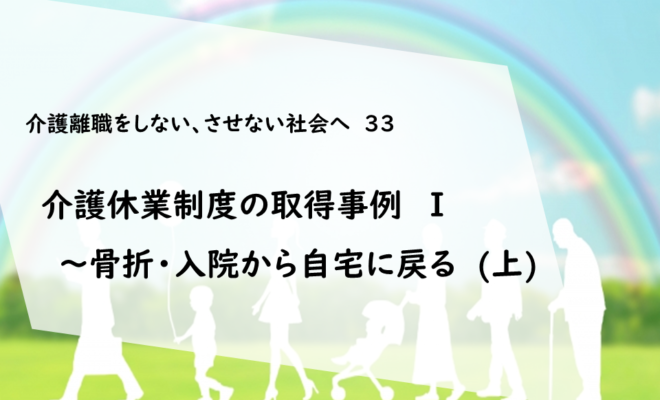


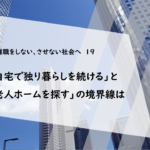



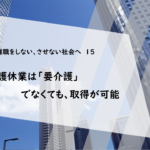

















この記事へのコメントはありません。