在宅介護のコアになるのは、訪問介護だ。
日本は、あと10年で、要介護発生率が顕著に高くなる85歳以上の後後期高齢者が1000万人に到達する。本格的な後後期高齢社会、要介護社会の到来だ。訪問介護が崩壊すれば、在宅介護は崩壊する。在宅介護が崩壊すれば、介護離職が激増し、経済・社会システムが破綻する。前回述べたように、それは東京の近郊都市から始まり、2040年までに全国を覆うことになる。
2024年の介護報酬の改定で、訪問介護の基礎単価が下げられたことから、「訪問介護を潰す気か」「介護報酬のマイナス改定で倒産事業者が激増した」と怒りの声が上がっている。
しかし、訪問介護の問題は、そう単純なものではない。仮に、訪問介護の介護報酬を改定前の水準に戻し、数%のプラスにしたところで、訪問介護の崩壊を食い止められないからだ。介護報酬だけではなく、在宅介護や訪問介護のシステムの課題を整理し、再構築しなければ、多くの地域で五年後には訪問介護を受けられない人が増加する。ここでは、訪問介護の再構築のために、避けては通れない四つの論点とその方向性について考える。
訪問介護に零細事業者が多いことのデメリット
現在の訪問介護のサービス提供体制の最大の問題は、零細事業者が圧倒的に多いことだ。
現在、訪問介護は、全国に約3万6千余の事業所がある。「令和3年度介護労働実態調査」によれば、訪問介護員数が4人以下という事業所が6.5%、5人~9人が23.9%。つまり、訪問介護員が10人以下の小規模・零細事業所が全体の三割、11,000事業所に上る。同様に事業所の利用者数が10人以下というところが14.5%を占める。
訪問介護というサービスは、労働集約的な介護サービスの中でも、介護効率性(一般的には生産性)が極めて低い事業だ。一人の介護スタッフが、一軒一軒の家を回るため、移動時間や手待ち時間も必要となる。八時間労働の訪問介護員が一日に介護できる人の数は7人~8人程度、実際の介護時間は5時間程度だろう。
訪問介護員が10人未満、利用者が10人未満となると、利用者が点在し、待ち時間も多くなるため、さらに効率性・生産性は低くなる。「小規模の介護サービス事業者の経営が逼迫している」という声が上がっているが、訪問介護というサービス特性・ビジネスモデルを考えると当たり前なのだ。「訪問介護の倒産は過去最高」とNHKを含め、新聞・テレビは煽っているが、倒産件数は81件。倒産率はわずか0.2%、廃業を合わせても1.4%しかない。逆を言えば、訪問介護員四人以下、利用者10人以下という零細の事業者がひしめき合っていて、これだけしか倒産していないともいえる。
「零細事業者は参入するな」と言っているのではない。ただ、事業というものは、すべて経営が安定するに必要な規模というものがある。最初はみんな赤字からスタートし、一定の規模になるまで我慢して、それでも必死に営業して規模を拡大するのだ。それはどんな事業でも同じだ。「零細零細事業所でも安定経営できるだけの介護報酬にしろ」と本当に思っているのだろうか。
零細事業者が多いことのデメリット
① 経営が不安定になる(倒産リスクが高い)
② サービスが不安定になる(離職・臨時休みでサービスが提供されない)
③ 訪問介護員が過重労働になる(有給が取りにくい・体調不良でも休めない)
④ 訪問介護員の給与が上がらない(報酬加算がとれない)
⑤ 訪問介護の常勤職ではなく、パート職員の比率が高くなる
⑥ トラブル・カスハラなどのリスクマネジメント対策が十分に取れない
⑦ IT化などの事務の効率化などの対策が十分にとれない
⑧ 指導や監査、手続き周知などの行政負担が重い
それは、経営が不安定になるというデメリットだけではない。
零細事業者だと、訪問介護スタッフが一人退職したり、体調不良で休むだけで、サービスが提供できなくなったり、他のスタッフへのしわ寄せが大きくなる。バックアップ体制が不十分なため、有給も自由にとることが難しいし、体調不良でも無理をして出勤しないといけない。利用者・家族とのトラブルなど、リスクマネジメントの対策にも限界があるし、IT化・ネットワーク化などの事務の効率化も進まない。ノウハウを構築することもできないし、給与も上がらない。常勤スタッフを雇う体力がないため、穴埋めのようなパートスタッフの求人ばかりになる。
零細事業者の吸収・合併圧力は強まる
これは、訪問介護員、介護労働者の給与・待遇が、その専門性と比較して十分か否かという議論とは別のものだ。ただ、介護サービスの中でも、特に訪問介護員の給与・待遇が低いのは、このような小規模の零細事業者がひしめき合っているからだ。それは介護行政の効率化にも影を落としている。零細事業者が多くなれば、指導や監査、手続き周知など行政の事務負担も増えるからだ。実際、専門の事務員がいないため、期間内に必要な報告が行われず、内容も不十分で何度も連絡しなければならないという声を聞く。
ミクロの視点、零細の訪問介護経営者の立場でみれば、訪問介護の報酬引き下げは経営に直撃する大問題だろうが、報道されているような【介護報酬引き下げ=在宅介護の崩壊】という構図ではない。逆に、地域全体の訪問介護のシステムの安定という視点で見れば、零細事業者は合併して、体力や効率性を上げてもらわなければ、訪問介護員の待遇も、地域全体の訪問介護サービスも安定しないのだ。今回の改定では、基本報酬は引き下げられているが、処遇改善加算を取れば、全体の報酬は上がる仕組みになっている。「処遇改善加算のハードルは零細企業には厳しい」という声が聞かれるが、その地域全体の訪問介護システムの安定を考えれば、当然のことなのだ。
ただ、この2024年の「基本報酬を下げて、加算を上げて、零細企業の合併を促す」という間接的な対策は、「介護報酬削減許すまじ」という反発を招いただけで、実際には、まったくその効果を上げていない。そのため、これからより厳しい、より直接的な「零細訪問介護の合併策」が行われることになるだろう。
これは、介護報酬を含めた国の政策的な側面と、自治体の地域包括ケアの中でのマネジメントの両面から行われることになる。基本報酬のさらなる引き下げや加算体制の見直し、事業者の指定基準の見直し、合併への一部補助などの強力なインセンティブによって、利用者が10人以下、スタッフが10人未満、パート職員比率が高いといった小規模・零細事業者は単独での運営は難しくなるだろう。
中小の市町村であれば、訪問介護の事業者数は一つでも構わない。それは極論ではなく、そうあるべきだと言ってよい。営利法人でも、社会福祉法人でもかまわない。利益優先ではなく、利用者・スタッフファーストで、まともな経営を行う事業者であるということが大前提となるのだが…。
【訪問介護の課題と再生 (全三回)】
訪問介護の課題と再生(Ⅰ) ~零細事業者の整理・統合~ 🔗
訪問介護の課題と再生(Ⅱ) ~集合住宅への訪問介護~ 🔗
訪問介護の課題と再生(Ⅲ) ~移動時間の報酬算定~ 🔗
<<< 介護のニュースを読む、ベクトルを掴む (TOPへ) >>>

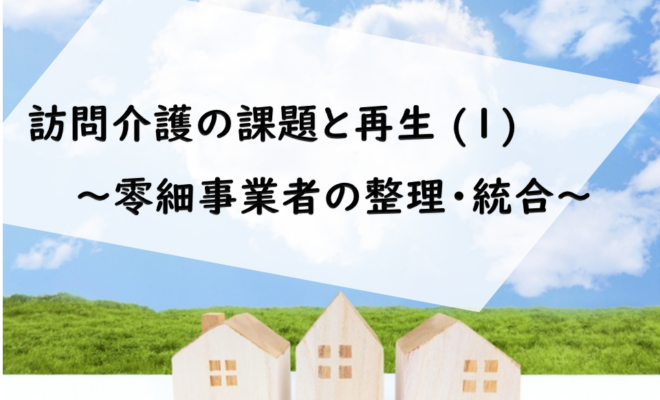























この記事へのコメントはありません。