日本経済新聞の一面トップに、「足りない特養、実際には空き、首都圏で六千人分」という見出しが躍った。日経新聞が都市圏の特養ホームを調べたところ、東京、神奈川、千葉、埼玉の特養ホームの計13万8千床のうち、なんと6千床が入所者がおらず空床状態だったというものだ。この地域の特養ホームの待機者は6万人とされているが、その一割に上る。特に、5年以内に開設された一部のユニット型特養ホームは空床率が「20~50%」と異常に高くなっているという。
これはどういうことだろう。
「特養ホームでは死亡退所から、次の入所まで一定のタイムラグが生じる」
「入所者を順次受け入れるため、開所から満床になるまで半年程度かかる」
そういった施設特性を考えると、「運営上発生する通常の空所」というところもあるだろう。ただ、記事の通り、運営上のタイムラグではなく、開所から数年経過しても複数のユニットやフロアが空いたままというところも多い。結果、入所者不足で、社会福祉・医療事業団への借入金の返済ができない社会福祉法人も増えていると聞く。
この「地域全体で見れば待機者はたくさんいるのに、一部の特養ホームは空所が目立つ」という現象は、東京近辺だけの話ではない。その理由は、大きく分けて3つある。
理由の一つは、介護スタッフの不足だ。特養ホームの運営、特にユニット型特養ホームにはたくさんの介護スタッフが必要となる。当然、どれだけ待機者がいても、介護スタッフが確保できなければ受け入れはできない。
実際、首都圏の社会福祉法人の理事長と話をすると、「特養ホームの整備計画が出ても、人材確保が難しいので応募できない」「市から新しい特養ホームを作ってくれないかと依頼があるが断っている」という話は多い。その計画に手を上げるのは、新しく開設した社会福祉法人や、事業拡大のために四国・中国地方など他の地域からやってくる社会福祉法人だという。域内の介護労働市場を十分に理解している近隣の社会福祉法人が断っているものを、そのノウハウも地の利もない事業者が参入して、必要な介護人材が確保できるはずがない。
ここには、都道府県の介護保険事業計画にも問題がある。数年前、神奈川県では駅を挟んで近隣の場所に、それぞれ50~100床規模の三つの特別養護老人ホームが同時に開設された。結果、介護看護スタッフの争奪戦となり、四月の開所に合わせて必要な介護看護スタッフが確保できたのは、人材確保・育成のノウハウのある社会福祉法人のみ。残りの二つは必要数の半数しか確保できなかったという。官民ともに、計画が甘いと言わざるを得ない。
二つ目の理由は、囲い込み型の「住宅型有料老人ホーム」「サ高住」などの台頭だ。
介護付有料老人ホームは、25万円~30万円というところが多いが、一部の住宅型有料老人ホームやサ高住は、15万円~20万円程度とユニット型個室の特養ホームと同程度の価格設定になっている者も多い。他のところでも述べている通り、制度矛盾や指導監査の緩さを突いたビジネスモデルであり、「認定調査の不正」「ケアマネジメントの不正」「書類介護の不正」など、介護保険制度の根幹に関わる不正が土台となっている。そもそも、同じ介護サービスを提供しても、介護報酬の適用方法で、一人当たり毎月数十万円の報酬差ができることは、誰がどう考えてもおかしいだろう。
低所得者対策が必要なのであれば、優良な高齢者住宅を限定して、家賃補助をすればよい。不透明な貧困ビジネスによる低価格化は、入居者にとっても、社会にとっても害悪でしかない。
【参 考】
反社会的 「貧困ビジネス」と化した囲い込み型高齢者住宅 🔗
「囲い込み」は、介護保険制度の根幹に関わる不正 🔗
ただ、特養ホームと同程度の価格帯の住宅型有料老人ホーム・サ高住であっても、「要介護高齢者・認知症高齢者の住まい」として比較した場合、そのサービスの質、手厚さは、天と地ほどの差がある。きちんと比較して選べば、「特養ホームよりも住宅型やサ高住を選ぶ」という人はいないはずだ。問題は、多くの家族、高齢者は、価格やサービスの質を冷静に判断・分析して、「終の棲家」を選んでいない、もしくは、選べる環境にないということだ。
特養ホームの場合、いまでも「待機者が多く、入所が難しい」と考えている家族は多い。そのため、申し込みをしても、いつ入所できるかわからないし、申し込みから入所まで一ヶ月程度は必要となるため、その間の生活をどうするかということも検討しなければならない。
しかし、このような住宅型有料老人ホームやサ高住の場合、病院から退院許可が出た日の午後には「申し込み、翌日すぐ入居可」というところもある。突然の骨折・入院で、「病院からは早期退院を求められているが、自宅に戻れない」という家族にとっては、「すぐ入居可」というセールストークに藁をもつかむような気持ちで、契約書にサインをしてしまう。
つまり、いまの特養ホームのシステムは、親の介護問題に直面して、慌てている家族のニーズには答えていないということだ。更に、家族のいない独居の要介護高齢者・認知症高齢者の場合、自分で「介護保険施設や高齢者の住まい」を選べないため、早期退院を望む病院は「紹介業者にお任せ」となる。その結果、自宅で生活できない要介護高齢者は、特養ホームではなく、高額の紹介料が得られる囲い込み型の住宅型・サ高住へと流れていくのだ。

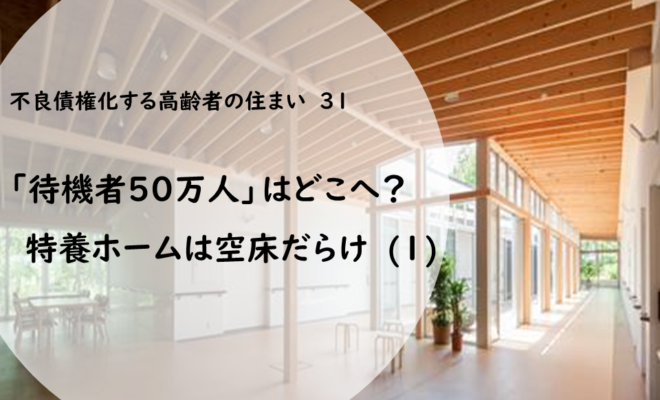
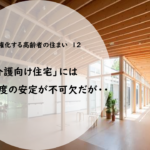



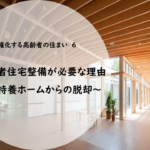


















この記事へのコメントはありません。