介護サービス事業、高齢者住宅事業は、介護保険制度から25年の間、異業種、他業種からの新規参入によって、その数だけは爆発的に増加した。
しかし、その多くは、介護の現場をしらないまま、「需要が高まるから介護はもうかる」「高齢者住宅ビジネスは利益率が高い」と盲目的に参入してきた素人事業者だ。
ただそれは、「介護や高齢者住宅のことを全く知らない」という笑い話では済まない。
法令順守・コンプライアンスの意識が乏しい
素人事業者の特徴、三つ目は、法令順守・コンプライアンスの意識が乏しいということ。
「介護が必要になっても安心・快適」とセールスするのであれば、重度要介護、認知症になっても対応できる介護システムを構築しなければならない。また、介護スタッフが安全に安心して働くことのできる環境を整えるのは事業者、経営者の仕事だ。しかし、高齢者住宅の経営者には、「介護看護はすべて現場に任せている」と、介護保険制度やケアマネジメントに関する最低限の知識さえない人が多い。
介護看護は高齢者住宅事業の根幹となるサービスであり、「介護のことはよく知らない」というのは、「自分の会社の商品・サービスが、どのようなものかよく知らない」と言うに等しい。「最終的な責任は経営者である私が……」と言うが、どのような法的責任・経営責任が発生するのかと聞くと、正確に答えられる人はいない。

このような、制度や法令を理解しようとしない経営者は、総じてコンプライアンスの意識が低い。消防法や労働基準法、労働安全衛生法なども知らないし、勉強しようともしない。囲い込みなどの問題が多発しているが、「それ法律違反ですよ」と説明しても、「それは現場が考えること」「他の高齢者住宅でもやっている」と、どこ吹く風だ。
全国で、事故屋トラブル、介護報酬の不正請求が起きているがこれらは氷山の一角でしかない。ただ、これら悪徳事業者は、「悪意を持って不正をおこなっている」と思っているかもしれないが、介護サービス事業者、高齢者住宅の事業者は、そもそも「何が不正なのか」を知らない、知ろうともしないのだ。
そんな経営者がたくさんいるのは、介護業界・高齢者住宅業界だけだ。
経営上・サービス上のリスクを理解していない
業種の如何を問わず、需要の増加がビジネスチャンスであることは言うまでもない。ただ、「需要が高まる」ということと、「事業性が高い」ということは同意ではない。要介護高齢者が増加しても、それを支える介護人材も介護財源も減っていくからだ。
優秀な介護看護スタッフの確保は難しく、介護報酬改定、自己負担の値上げなどの「制度変更リスク」も高い。転倒骨折、誤嚥窒息などの事故、入居者間のトラブル、感染症や食中毒、火災や自然災害、入居者・家族からの苦情などサービス上のリスクも大きい。経営管理やリスクマネジメントの知識・ノウハウなしに継続できるような事業ではない。
それを理解せず、「需要が高まる」という一点集中の過剰な期待によって、異業種・他業種から経験もノウハウも最低限の知識さえない素人事業者が大量参入してきた。結果、過重労働で介護現場は疲弊、事故やトラブル、クレームが多発し、現場からは「介護の仕事はブラックだ」と怨嗟の声が溢れているのだ。介護という仕事がブラックなのではなく、介護現場で何が起きているのか、スタッフがどれだけ疲弊しているのか、知らないし知ろうともしない素人経営者が介護業界には圧倒的に多いからだ。

これら素人事業者の特徴は、個人・中小事業者だけではない。大手だからノウハウがあるだろう、経営が安定しているだろうと思うのは大間違いだ。介護保険発足当初、介護ベンチャーの旗手と呼ばれた「コムスン」、介護や高齢者住宅のプロを自称した「ワタミの介護」、低価格介護付有料老人ホームで事業所数業界ナンバーワンとなった「メッセージ」、すべて経営者は変わっている。信じられないような事故やトラブル、事件が多発しているのは、人材育成が整わないまま急拡大してきた大手事業者に多い。
「事業に対する意欲が重要で、経営・サービスノウハウ・知識は後からついてくる」
「高齢者住宅は新しい事業だから、十分な経営ノウハウが不足しているのは当然だ」
識者の中にはそう庇う人がいるが、それは考えが甘い。
当選後に「いまから勉強します…」が通用するのは政治家くらいだろう。素人経営者が作った高齢者住宅は商品設計・事業計画の段階で破綻しているからだ。高齢者住宅への入居契約は長期契約であるため、途中で価格設定やサービス内容を大幅に変更することはできない。車いす利用者が増えても居室や食堂配置は変えられない。経営を続ける中で、スタッフが集まらず、事故・トラブルが多発し、「こんなはずではなかった」と気づいても遅いのだ。
現在の高齢者住宅の商品設計、ビジネスモデル上の欠陥は大きく分けて三つある。
① 重度要介護・認知症になれば生活できない重度化対応力の不備
② ケアマネジメント・認定調査などの不正が横行する「囲い込み」
③ 不透明な経営、自転車操業になりやすい入居一時金経営
実は、このような脆弱な高齢者住宅が、大手を含め八割を超える。
素人事業者が「目先の利益ありき」で作った脆弱な高齢者住宅の特徴を解説する。
【悪質な事例としてご参照ください】
サンウェルズの「PDハウス問題」 囲い込みのパンドラの箱はいつ開く(上)
サンウェルズの「PDハウス問題」 囲い込みのパンドラの箱はいつ開く(下)

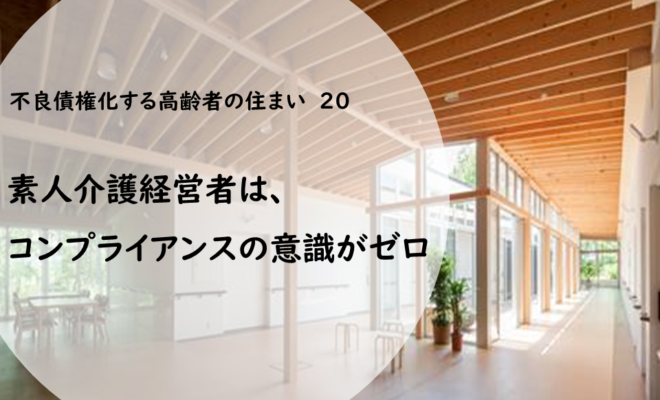




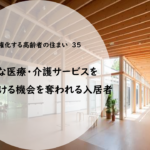




















この記事へのコメントはありません。