入居後に発生する喧嘩やいじめなど、他の入居者との人間関係のトラブル。トラブルや苦情対応の基本は、定期的な家族との面談、相談体制、サービス管理体制が整っていること。「全てお任せください・・」「ご不満やご心配はいつでも言ってください・・」しか言わない事業者は素人。
高齢者・家族向け 連載 『高齢者住宅選びは、素人事業者を選ばないこと』 021
年齢を問わず、進学や就職など、新しい生活のスタートは、「期待と不安」が入り混じるものです。
特に、高齢者住宅への入居は、高齢者本人にとっても、家族にとっても、大きな「新生活への不安」を抱えた決断です。年をとってから住み慣れた自宅を離れて転居するのは、精神的にも大きな負担ですし、それを見守る家族にも「自分が介護できなくて・・」という申し訳なさが漂っています。
高齢者住宅への入居後に、安定した快適な生活を送っている人もいますが、一方で、高額な一時金を支払ったにもかかわらず、「馴染めないから・・」「他の入居者と話が合わない」などで、途中退居する人もたくさんいます。中には、家族が訪問するたびに、「早く家に帰りたい・・」「こんなところは嫌だ・・」と泣きつかれ、それでも自宅では生活できないために、つらさと悲しさで家族も泣きながら家に帰るという話も少なくありません。
「自宅に帰りたい」という高齢者の訴えは、「寂しさ」「ホームシック」などもあり、すべてが事業者の責任ではありませんし、また事業者が、家族間、入居者間の人間関係に過度に立ち入ることは、本来好ましくありません。「入居者間のトラブルは無関係」という立場をとっている事業者もあります。
しかし、人間関係のトラブルで安全な生活が脅かされる、他の入居者とのトラブルや意地悪が原因で退居せざるを得ないということになれば問題です。
人間関係のトラブルの内容は、要介護状態によって変わる
実際にどのような入居者間トラブルが発生しているのか、いくつか例を挙げてみましょう。
| 高齢者住宅の入居後に発生するトラブルの例 ◆ 耳が悪いのか、大音量で音楽やテレビをかけるなど、隣人がうるさい。 ◆ 食堂で近くの席の人が、タバコの臭いがひどく、食事が食べられない。 ◆ 何が気に入らないのか、睨みつけたり、大声で怒鳴ったりする。 ◆ 一部の仲良しグルーブが仕切っており、仲間に入れず疎外感がある。 ◆ 隣の部屋の高齢者が、何度も間違えて部屋に入ってきて困る。 ◆ 部屋の中に置いてあった、財布がなくなった。 |
このように整理すると、通常の集合住宅や学生寮、社員寮などと同じようなトラブルだと思うでしょう。
ただ、その特徴は、要介護状態によって分かれるということです。
要介護4、5という重度要介護高齢者が中心の介護付有料老人ホームでは、寝たきりなどで自室にいることが多く、深刻な人間関係トラブルはそれほど発生していません。
これに対して、自立~要支援、軽度要介護高齢者の間では、人間関係も濃密なものになりますから、様々なトラブルが発生します。入居者同士の大喧嘩や、金銭関係トラブル、男女間の恋愛、それに関わるトラブルなど問題も大きくなります。養護老人ホームやケアハウスでは、入所者同士の暴行事件や殺人事件まで発生しています。
今後、増えると考えられるのが、認知症の周辺症状によるトラブルです。
認知症になると、直前に起きたことを忘れる記憶障害や、筋道を立てて思考できなくなる判断力の障害といった中核症状がでてきます。そのため、自分がどこにいるのかわからなくなったり、他の居室に勝手に入るなどのトラブルが起こることになります。更に、幻覚を見たり、妄想を抱いたり、暴言や暴力を振るったり、徘徊したりといったBPSD(周辺症状)によるトラブルも報告されています。また、清潔・不潔の感覚が鈍くなり、部屋からひどい悪臭がしたり、寝タバコで畳が焦げるなど、一歩間違えば火災につながりかねないといったケースもあります。
認知症であっても、寝たきり状態であるなど身体機能が低下している場合は、周囲に及ぼす影響は少ないのですが、身体的な自立度が高い高齢者の認知症は、暴言や暴力など周囲の入居者の生命、生活への影響が大きくなるのです。
日々の様々な困りごとに対する相談サービスや人間関係トラブルへの対応力は、安心して生活するためには不可欠であり、高齢者住宅選びの大きなポイントの一つです。
大喧嘩や金銭関係トラブル、いじめなどの問題など、入居者や家族から相談のあったときに、どのように対応するのか、そのノウハウは、事業者によって大きな差があります。
相談サービスは、高齢者住宅の能力・レベルを測ることのできる大きな指標だと言っても良いでしょう。
不安やトラブルに対応できる相談体制が整っているか
まず一つは、きちんとしたサービス管理体制・専門的な相談体制が整っているかです。
有料老人ホームの場合は、制度基準の中に「生活相談員」の配置が義務付けられています。一方、サ高住でも、生活相談サービスは必須だとされていますが、高齢者住宅事業者が直接提供しておらず、他の事業者との別契約のところもあります。
第一のチェックポイントは「サービス管理体制」です。
生活相談は、単なる入居者間トラブルや困りごとへの対応だけでなく、「入居者と家族」「入居者間同士」「高齢者住宅と家族」をつなぐ架け橋でもあります。いじめ、金銭問題など、トラブルの内容によっては、双方の意見を聞きながら、時間をかけて調整する必要もでてきます。
そのため、サ高住であっても高齢者住宅事業者の責任で提供されているのが基本です。
そうでなければ、様々な調整がスムーズに行えないからです。また、契約や退居要件に関わる問題もでてきますから、「ホーム長」などのサービス管理者が設置され、全体として、組織的なサービス管理体制が構築されていることも必要です。
生活相談員の資質・資格も重要です。
事業者の中には、低価格化のために、生活相談員が「介護スタッフと相談員が兼任」「他の事業者との兼務」というところがありますが、それでは、いつ誰に、相談して良いのかわかりません。
優良な事業者は、社会福祉士などの専門的な国家資格をもった社会経験、介護経験のある優秀な生活相談スタッフが、専属・専任で配置されています。
もう一つは、「定期的な相談機会の確保」です。
経験豊富なプロの事業者は、入居初期は入居者・家族の不安が大きいことはわかっています。
そのため、一ヶ月、三ヶ月毎に定期的な家族面談の機会を設け、積極的に「何か困りごとはございませんか?」「不安なことはありませんか?」と事業者から積極的に聞いてくれます。少し慣れてくれば、6ケ月に一度のケアカンファレンスで、相談や質問をすればよいのです。
「トラブルや困りごとはいつでも相談してください・・」「スタッフにいつでもお声がけください・・」というところは多いのですが、バタバタと忙しく働いている介護スタッフを捕まえて、「実は・・ちょっとご相談が・・」と話かけられるはずがありません。
「いつでも・・・」「誰にでも・・」というのは、実際には話を聞く気がない素人事業者の常套句だといって良いでしょう。
見学・相談時に、トラブルに対する不安を投げかけてみる
このトラブル対応力はトラブルが起こるまでわからない・・と言う訳ではありません。
ほとんどの高齢者住宅で、入居相談・入居説明に対応するのは、管理者か相談員です。
ですから、その相談員の受け答えで、その事業者のサービスの質が図れるのです。
様々なタイプの生活、生活歴の高齢者が生活しているのですから、全員が寝たきり、重度認知症でない限り、人間関係のトラブルは必ず発生します。
その質を見分けるポイントは、入居相談時にトラブルの不安や質問を投げかけてみることです。
「うちの父親は、頑固なところもあるので、溶け込めるか心配」
「母親は、引っ込み思案で人付き合いがうまくないので、不安が大きい」
経験が乏しい相談員は、「多分・恐らく」「安心・快適」「みんな仲良し」といった美辞麗句しか返ってきません。それは、入居者間のトラブルを軽く考えており、その対応力も乏しいということです。
これは、介護事故の問題と良く似ています。
身体機能の低下した高齢者の集合住宅ですから、「トラブルゼロ」ということはありません。
高齢者住宅を選択するにあたって、大切なことは、入居者同士の人間関係トラブルを理解し、対応策も含め丁寧に入居希望者・家族に説明できる事業者を選ぶということです。どのようなトラブルが発生する可能性があるのか、それに対してどのような予防策をとっているか、それにどのように対応するのか、事例を挙げて説明できるところは、それだけノウハウや経験があります。

もちろん、トラブルはすべて事業者だけで対応できる問題ではありません。
「初期の段階では、不安が大きいのでなるべく頻繁に訪問してください」
「訪問が難しければ、お電話いただくだけでも、落ち着かれる方は多いです」
といったなど、家族への提案や協力も大切です。
「介護できないのが申し訳ない」と悔やむ必要はない? で述べたように、高齢者住宅・老人ホームに入居しても、家族の役割は何も変わりません。「事業者にお任せ下さい」ではなく、家族と高齢者住宅が連携して、本人が安全・安心、快適に生活できるように一緒に支えていくという認識の高齢者住宅がプロの事業者です。
その架け橋となる生活相談員の役割は非常に大きいのです。
「すべて、お任せください」「安心・快適」と胸をはる事業者、相談員は信頼できるように見えますが、間違いなく素人なのです。
「ほんとに安心・快適?」 リスク管理に表れる事業者の質
⇒ プロと素人事業者の違いは「リスクマネジメント」に表れる ?
⇒ 「こんなはずでは…」 入居後のリスク、トラブルを理解する ?
⇒ 「転倒・骨折…」 多発する介護事故の原因とその責任 ?
⇒ 介護事故の対策と、その説明から見える事業者の質・ノウハウ ?
⇒ 「いじめ、認知症…」 トラブルの対応から見える事業者の質 ?
⇒ 「火災・地震・自然災害」 防災対策に表れる事業者の質 ?
⇒ 「インフルエンザ・O157」 感染症・食中毒対策に表れる事業者の質 ?
⇒ 「100%満足はない」苦情・クレーム対応に表れる事業者の質 ?
⇒ 「聞いた費用と違う」 金銭トラブルを起こすのは悪徳事業者 ?
⇒ 「突然の倒産・値上げ」 最大のリスクは事業者の経営悪化 ?
⇒ 入居者・家族にとっても無関係でない「報酬・制度改定リスク」 ?
高齢者住宅選びの基本は「素人事業者を選ばない」こと
☞ ポイントとコツを知れば高齢者住宅選びは難しくない (6コラム)
☞ 「どっちを選ぶ?」 高齢者住宅選びの基礎知識 (10コラム)
☞ 「ほんとに安心・快適?」リスク管理に表れる事業者の質 (11コラム)
☞ 「自立対象」と「要介護対象」はまったく違う商品 (6コラム)
☞ 高齢者住宅選びの根幹 重要事項説明書を読み解く (9コラム)
☞ ここがポイント 高齢者住宅素人事業者の特徴 (10コラム)
☞ 「こんなはずでは…」 失敗家族に共通するパターン (更新中)


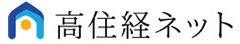






















この記事へのコメントはありません。