母の死後、介護が必要になり介護付有料老人ホームに入居した父。ホームの生活にも慣れ楽しく暮らしていたものの、病院と結託した「かかりつけ医」によって入院させられ、一気に要介護度が悪化、食事もトイレもできない寝たきり状態に・・・
高齢者・家族向け 連載 『高齢者住宅選びは、素人事業者を選ばないこと』 059
入居者・・・実父(90代前半)、認知症あり、要介護3
自宅で母が、心筋梗塞で突然亡くなり、突然、一人暮らしになった父に認知症の症状が現れ始めました。
私たち(次女夫婦)は、父の家から徒歩10分程度のところにあります。姉夫婦も同一市内にいましたので、訪問介護や定期的にショートステイを利用しながら、毎日通って3年ほど介護を行いました。食事(調理や準備は家族)やトイレなどは一人でできることや、入浴も見守りをしていれば自分で入れるので、それほどの手間はかかりませんでした。ただ、トイレの失敗が増えてきたことや、レビー小体型認知症で幻覚なども少しずつ悪化してきたことから、介護付有料老人ホームに入居することにしました。
自宅で介護できなくなることは想定していたので、在宅介護の2年目くらいから高齢者住宅について本を読んだり、いくつもの老人ホームを見学して探していました。
ユニット型で【2:1配置】で、認知症や医療ケア対応も可能、医師も定期的に訪問診療を行っており、看取りも可能だという話を聞いて、ある介護付有料老人ホームに入居しました。入居一時金は300万円程度、月額費用の支払いも28万円程度(日用品・医療費含む)と、それなりに高額だったのですが、父は90歳を超えていましたし、貯蓄を取り崩しても十分に支払い可能だと判断しました。
私と姉の家、どちらからも車で20分程度と近いところを選んだので、外出や買い物のついでなどに気軽に立ち寄ることができ、2日に1度は会いに行っていました。
入居当初は、ショートステイと勘違いしているようで、「もう、帰る日か?」と言っていましたが、「家に帰りたい?」と聞くと、「別にここでもええ、もうちょっといる」と本人も納得しているようで、若い女性の介護スタッフの方から剽軽なことを言って笑わせていると聞き、父の違う側面を見たようで「この老人ホームを選んでよかった・・」と思っていました。
そんな生活が2年ほど続いたある日、ホームから父が入院したとの連絡が入りました。年齢も90歳を超えており、どこかで覚悟はしていたものの、前々日に訪問した時は、全く変わりがなかったため、「心筋梗塞か・・・」「脳梗塞なのか・・・」と驚いて病院へと向かいました。
病院につくと、相部屋が空いていないということで、個室に入っていました。
しかし、ベッドに寝ていたものの、本人の様子はいつもと変わらず、医師から何の説明もなく、また看護師に聞いても、「通院時に異常が見つかって、そのまま入院した」というだけで、何の病気で入院したのかさえわかりません。「通院なんかしてないはずなのに」「重大な感染症などが見つかったのか」など、不安なまま姉とも話し合いましたが、医師は「今日は忙しく説明できない」「明日も明後日も休み」とのことでつかまりません。
ホームの方が着替えなどの一応の入院準備を持ってきていただいたのですが、足りないものもあり、ホームの看護師さんとも話をしたのですが、「私たちにもよくわからない」「先生(医師)の判断なので」とことで困惑されている様子でした。
結局、入院から4日後に医師から話を聞けたのですが、その協力病院の医師であり、かつホームの訪問診療も行う担当医はよぼよぼの高齢の方で、「少し肝機能が悪かったので、念のため、検査をしようと思って」「入院期間は2週間くらいだと思います」とゴニョゴニョと話をされるだけでした。
それよりも驚いたのが病院の対応です。一日の利用料が1.5万円もするトイレ付の広い個室に入ったのですが、トイレに連れて行ってくれるわけでもなく、父が自分でベッドから降りようとしたために「転倒すると危ないから・・」とベッド柵で囲われ、降りられなくなっていました。姉がいるときにトイレに行きたいと言ったそうで、それを病院の看護師さんに伝えると「オムツをしていますから、その中でしてください。後で替えますから・・」とこともなげに言われたそうです。食事の時に介助に行くと、鳥に餌をやるように、無理やりスポイトのような注射器で食べさせられていました。
一般の病院ですから看護師さんも忙しいことはわかりますし、老人ホームと介護機能が違うことはわかります。ただ、父があまりにも可哀そうだったため、ホーム長さんと、「他の方に迷惑がかかるような病気でなければホームに戻してやってほしい」「父が急変して亡くなっても、ホームの責任は問わないから」「急変や転倒しても家族が責任を持つと念書を書いても良い」とお願いし、「私から担当医に話をします」との言葉をいただきました。
それでも、調整が必要だったのか、結局15日程度の入院となり、その間、毎日、姉と私と交代で食事の介助などに病院に行きました。うるさい家族だと思われたのか、入院中も退院の時も、医師から肝機能の検査結果についても何の説明もありませんでした。
ようやく退院できたのですが、その時には父は、一人では歩くこともできず、トイレにも行けず、一人で食事もできないような状況になっていました。
それまでホームでは朗らかでよく笑っていたのですが、認知症が一気に進み、表情もなくなり、自分から何かを話すことは全くなくなり、全く違う父になってしまいました。そして、それから三ヶ月程度で、母と同じように、夜中に心筋梗塞となり、眠ったまま亡くなりました。
通夜や葬儀には、忙しい中で夜勤明けや夜勤前の忙しい中、ホームからたくさん焼香に来ていただき涙がでました。初七日が終わり、退居の手続きなどを含め、あらためてホームにお礼にお伺いした時、ホーム長やユニットリーダーの方から「力不足で申し訳ない」と謝罪され、また涙がでました。
ホーム長をはじめ、介護スタッフの方には大変感謝していますし、いまでも良いホームを選んだと思っています。ただ、医師から「入院が必要だ」と言われると、看護師や介護スタッフは抗弁することができないとのことでした。またスタッフの方と話をすると、今回のようなケースは他にもあり、介護の仕事に限界を感じて辞めてしまう人も少なくないとのことでした。
もちろん、ホームは病院ではありませんので、感染症や骨折など対応できないこともあると思います。ただ、90歳の高齢者を無理やり入院させ、ベッドから出られないようにすれば、歩けなくなったり、トイレに行けなくなるのは当然のことです。姉が知人の看護師に話を聞いたところ、「医師が入院理由、病状の説明を家族にしないのは信じられない」「病院都合で、個室代をとるのは法律違反」と言われたそうです。老人ホームの方には良くしていただいた分、父を廃人にしたあの医師と病院に対しては、残念というよりも、今でも許せない気持ちで一杯です。
【失敗の原因は何か・・どうすればよかったのか・・】
医療は、介護同様に高齢者・要介護高齢者にとっては日常的に必要となるサービスの一つです。感染症や骨折など一定入院が必要なケースはあります。
ただ、高齢者の場合は、「病気を直せばよい」「数値を正常に戻せばよい」というものではなく、薬剤が転倒・骨折などの原因となったり、入院がADL(日常生活動作)の大幅な低下を招く、認知症が一気に進むという副作用やリスクも大きくなります。
高齢者住宅を選ぶ場合、「介護の手厚さ」や「建物設備」「サービスの評判」などその高齢者住宅について、比較検討し、厳しくチェックする人は増えていますが、「医療体制」や「協力病院」までは、理解やチェックが及ばないものです。そのため、「協力病院」と言っても高齢者・要介護高齢者の疾病や病気、副作用やリスクを全く理解せず、上記の例のように「老人ホームの入居者」をクイモノにして利益を上げようという病院、医療機関も少なくありません。ホームは気に入っていたのに、入院でめちゃくちゃになった…という話は多いのです。
これは、診療所や病院にとって「高齢者住宅の入居者は良いお客さん」というところもあるからです。
自宅で生活する高齢者が入院するとADLが大きく低下するため、自宅に帰ることができなくなるため、長期入院になりがちです。一方、介護付有料老人ホームや特養ホームだと、看護師がいるので、病院の都合で入院させ、すぐに退院させることができます。
また、老人ホームは医療行為ができないため、病院や医師に頼らなければならず、家族は老人ホームとの関係があるため「不必要な医療や入院はやめて…」と強く言えません。中には「介護付有料老人ホームの入居者はお金があるから…」と希望していないのに勝手に個室に入れられるということもあります(ベッドが空いていないなど病院都合で個室を利用する場合、個室料を取るのは違法です)。
これは協力病院だけでなく、協力診療所も同じです。
家にいるときは、月に二度の診察で、高血圧の薬しか飲んでいなかったのに、老人ホームに入ると、家族への相談もないまま、複数の内科、精神科、眼科、歯科、整形外科などの協力診療所の受診を受け、毎月、診察、治療、投薬をして、無駄な医療費が5倍にも6倍にもなるというケースもよく耳にします。
特に、相談例のように、訪問してくれる診療所と協力病院が同系列の場合、そのリスクはダブル、トリプルで高くなります。 残念ながら、高齢者や患者を「医療費搾取のツール」程度にしか考えていない医師も多いのです。
もちろん、そのような協力病院・診療所ばかりではありません。
見分けるためには、実際にどのような病院が協力病院になっているのかを調べてみることです。最近は、インターネットなどでも、病院の口コミサイトがありますから、一度チェックしてみると良いでしょう。
また、入居前に、「医療のことが心配なので、協力診療所の医師の方とお話できますか?」と聞いてみるのも一つの方法です。「いつでもOK」というわけではなく、時間の制約はありますが、入居希望者の病状や医療ニーズに関しては、高齢者住宅も医師も気になるところでしょうから、聞いてくれるはずです。その時にかかっている病気や「できるだけ入院させたくない…」「看取りについて…」など質問すれば、専門的な視点からの医療的サポートや看取りのリスクなどについて、説明してくれるはずです。
医師との面談が難しくても、担当者に「高齢なので延命だけの無理な医療行為や入院はさせたくないのですが…」「高齢者に対する過剰な医療行為が社会問題になっていますが…」と質問をぶつけてみましょう。感染症や骨折など入院が必要なケースもあり、またホーム内の医療行為にも限界もありますから「絶対に入院させない」ということはできません。ただ、そのホームの担当者がどのように答えるのかによって、ホームと病院との力関係や入院の副作用についてどの程度真剣に考えているかが見えてきます。
「そんなことはしていない」「忙しいからダメ」「病気はホームでは対応できないので病院にお任せ」というところは、その程度だということです。
「こんなはずでは・・・」 高齢者住宅選びに失敗した家族の声を聴く
⇒ 【F053】 高齢者住宅選びに失敗している家族に共通するパターン ?
⇒ 【ケースⅠ】 病院から紹介された有料老人ホームに入居したが ?
⇒ 【ケースⅡ】 「介護が必要になっても安心・快適」はイメージと正反対 ?
⇒ 【ケースⅢ】 生活保護受給者をクイモノにする悪徳高齢者住宅 ?
⇒ 【ケースⅣ】 高額の入居一時金を支払ったのに ~要介護対応の不備~ ?
⇒ 【ケースⅤ】 高額の入居一時金を支払ったのに ~トラブル退居~ ?
⇒ 【ケースⅥ】 「協力病院」の医師に無理やり寝たきりにされた父 ?
⇒ 【ケースⅦ】 不正を訴えても「自己責任でしょ・・」と無関心の役所?
⇒ 【ケースⅧ】 家族が住む近くに高齢者住宅を探せばよかった ?
⇒ 【ケースⅨ】 意見や希望を上手く伝えられずにストレスに ?
⇒ 【ケースⅩ】 月額費用の説明に対する誤解がホームへの不信感に ?
高齢者住宅選びの基本は「素人事業者を選ばない」こと
☞ ポイントとコツを知れば高齢者住宅選びは難しくない (6コラム)
☞ 「どっちを選ぶ?」 高齢者住宅選びの基礎知識 (10コラム)
☞ 「ほんとに安心・快適?」リスク管理に表れる事業者の質 (11コラム)
☞ 「自立対象」と「要介護対象」はまったく違う商品 (6コラム)
☞ 高齢者住宅選びの根幹 重要事項説明書を読み解く (9コラム)
☞ ここがポイント 高齢者住宅素人事業者の特徴 (10コラム)
☞ 「こんなはずでは…」 失敗家族に共通するパターン (更新中)


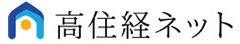






















この記事へのコメントはありません。